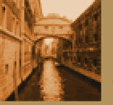

バックナンバー〜2009年9月までの分
最新版は公式ブログで更新中です。
自分の価値をイメージし続けて
自信がなくなるとき、一体何をやっているんだろうと思うときがある。
そんなときは、瞑想して、これまで人が褒めてくれたこと、認めてくれたことを
思い出して、自分の良いところを挙げてみる。
そして、自分はこんなふうに役に立つとか、こんなふうに喜ばれることもあると
自分の価値を素直に認めることができる。
ともすると世間との相対的な比較や情報の洪水の中で
自分の真価を判断できないことがある今日この頃。
人に元気を与える、人をしばし幸せな気持ちにできるだけでも、生きている価値がある
そうだ。人と比べるのではなく、人の言葉に左右されず、自分が五感で体験・確認してきたことがすべて。誰にでも、「その人固有の価値」がある。
自分に感動する瞬間を
人は人に感動を与えることもできるが、そのことを通じて、自分自身が感動できる。
実はそのことが一番幸せだったりする。
話をしたり、歌ったり、演奏したり・・・いろんな表現で伝え、人の心が少しでも動くことを感じると、またその感動が長く消えずにいてくれると、生きていてよかったと思う。相手の心に長く存在できることが最高の幸せ。
自分に感動できる人こそ、人生をより濃厚に生きることができ、それを糧に何かを世に残そうと行動するのではないか。これからでも遅くない。少しでも、何かを伝え、遺したい。
目を閉じて、心を開く。
都会の喧騒のなかで、情報に埋もれる生活のなかでは、目を開けっ放しの生活が続く。
そんなときは、心の窓は閉じている。
肉体も疲れ、乾き、危機的な気持ちになるとき。そんなときは、目を閉じて、
ゆっくりと呼吸をしてみよう。そうすると心の窓が開き、潤いが生まれる。
ある本でこんな1行をみつけた。
Take the time to stop sometimes and smell roses.
ゆっくり過ごせば、バラのいい香りもする。
急ぎすぎれば、人生の楽しみも味わえないという教訓。自戒の念を込め。
一生懸命だから壁にぶつかる。だから良し。
一生懸命やれば悔いはないというけれど、そのとき全力を出したつもりだけれど
終わってみれば反省、反省。実力を疑ったりする。でも、落ち込むことはない。
一生懸命だから悩む、一生懸命やったから次の課題が見えているのだ。
悩めばまた次の手を考える。壁にぶつかることはそれを越えるためのステップ。
壁に行き着かないより、ずっとよい。壁にぶち当たる痛さを感じた人は、強くなれるから。
皆、ステージに上がりたい
情報の送り手と受け手という役割が明確であった時代は終わり、今や生活者も立派な情報発信者。自分が関わったものに対し、モノ申したい、何かを伝えたい、それをすることで社会に参加したい、つながっていたいという欲求が高まっている。
インターネットを大きな劇場とたとえれば、ステージがどんどん大きくなって、演者が増える一方。それは人間の本質的欲求か。・・・言いたい、賛同されたい、認められたいの自己表現。
いかにステージでキラリと光るアクターを探せるか。受け手(観客)は、質がよく、役にたつ、心地よい「情」報を選ぶのかという責任をもたねばならない時代になった。
18歳の自分がライバル
30年近く前にできたことが、今できないことがある。それは体力の問題、加齢のせい?と理由はいろいろあろうが、明らかに努力を怠ってできなくなったものについては、その理由は当たらない。今からでも努力をして、なんとかあの頃と同じようにやってみたい。そう思い、練習を再スタート。あのときの自分を思い出し、できる、やれると自分を鼓舞し続けて、毎日そのことを頭に描く。
必ず、18歳のときを越えた結果を出そうと思っている。ピアニスト、バレリーナは練習を1日、3日と練習を怠った分成長が止まるといわれているなか、30年の遅れを取り戻せるか?
拍手を、涙をありがたく。
何かを伝えたいと思って行動している人間にとっては、相手の反応がすべてである。
いつも相手の顔を見る。理解されているか、賛同を得ているか、その反対か、心に入っているか、不快と思われていないか・・。
実はビクビクしながら一挙一動している一面もある。
その様子を伺いながら、ストーリーを展開していく。
そしてクライマックスにお客様の顔を見る。拍手の強さ、あたたかさ、声援、花束、そして涙。くしゃくしゃの顔、化粧の落ちた顔をみつけると、なんともいえない気持ちになる。人は泣くことで心を浄化する。泣く分だけ心がキレイになる。
人が泣くのを静かにうれしいと思う、因果な仕事?生き方?は誇り。
老いた女優が美しく
素晴らしい作品は演者が変わっても料理の味付けが変わったように楽しめる。
もっとも気に入っているミュージカルCHICAGO、すでに何度もチェックし、プロの意気込みをどっぷり感じてきたが、このたびの主役、前回と違い大柄な黒人と小柄な白人のコンビ。白人の女優はどうみても老女である。しかし、時間を経るほどに彼女の演技は黒人パワーを圧倒する存在感を増し、貫禄いっぱい、魅力いっぱいにステージを飾った。この仕事が好きでやっている、好きでたまらない、これがわが人生。と彼女が全身で話しかけているようだった。人生を賭けてできることがあると、生命力も増し、美力も増すのだ。人は自分次第でいつまでも、美しく生きることができる。ハンディキャップをプラスに。老いをプラスに。
心のふるさとはいくつ?
岐阜、京都、東京、新潟、NY、パリ、ナポリ・・・。生まれ、育った、棲んだ、
訪問した、いろんな関わり方はあれど、自分自身を取り戻せる処が、「わが心のふるさと」である。その土地それぞれに、違った自分が芽生え、その後の人生にさまざまな影響をもたらしている。
心のふるさとは、たくさんあって幸せ。目を閉じればいつでもそこに帰ることができる。人生の終盤はそのふるさとのいずれに戻るのか、まだ新しいふるさとを探し続けて逝くのか?
すべての記念日は、〜これまでも、これからも「ありがとう」〜
大切な節目のときの言葉として、ある方に贈ったこの言葉。
考えついたあとで、意外にいいと自画自賛。
ビジネスの節目も、誕生日も、結婚記念式でも出会いの日でも・・・
とにかくこの一言でいい。この一言がよい。
そして、ずっとずっと「これからも」といえると、尚うれしい・・・。
「私の川」に流せば
つらいこと、いやなことがあったら、「私の川」に流せばよい。その川は私の海に向かう。
私の海とは私の夢。どんなことも、私の明日のために、ありがたい糧になる。
もちろん楽しいことや、うれしかったことも、いつしかそこに自然に流れていく。
「私の川」をもっていることが、今の時代を生きる強さになる。
人を見る、手を見る。
男の人も爪を磨く時代らしい。ビジネスの現場では靴を見るだけでなく、指先もチェックされるとか。
そんななか、農業青年たちに会った。彼らは農作業を終えて、着替えて会いにきてくれる。
手を見たら爪の中には、土が入ったままの状態。
思わず自分の手を引っ込めた。パソコンで先が痛んでいるのを隠そうとマニュキュアなんかして。上からごまかしているような自分が恥ずかしい。彼らの手が、指が爪が彼らの素敵な生き方の象徴であると、その手からお土産にと渡された米粉のパンをほおばりながら涙ぐんだ。素敵な指先であった。
「なんで、そこまでしてくれるんですか?」
農業青年のひとりが、会話の途中でそういった。「そんな本気な人を見たことがないです」。
きらきらした目のすっぴん顔でそういわれた。「いや、別に。なんか放っておけないだけ。そんな勝手な気持ちかな」そういうしかなかった。
あとでその言葉を思い返し、とてもうれしく何度も何度も思い出した。
人のお役に立てるかどうかは、時としてお節介になることもあり、余計なことはしないほうがいいといわれることも多い・・・が、したほうがよいと思うときはすればよい。
自分の気持ちが人に通じたときほど、うれしいことはない。そんなことがあると人生は今日も晴れ。である。
土壇場力って大事かも
どんなに準備して臨む講演だってそのパソコンが壊れることもある、何が起きるかわからないのがビジネスの世界。人生もまったく同じ。そんなときには、土壇場力・現場力。
何があってもいいように万全なる準備をするはもちろん、もし、これは困った!という事態になっても、身一つで切り抜ける力。原稿がないとできません!といっている場合ではない。それこそ日頃からの経験の積み重ねか。
カラダ張ってる?本気でやっている?
小さなことでくよくよしはじめたら、心のチャンネルを変えて、そう悩めるほど、五体満足で生きていることに感謝しよう。うじうじしてないで、夢に向かって突き進もう。
それってカラダ張ってる?本気でやってる?と自問したら、おそらく「いいえ」とつぶやくだろう。カラダ張っている人はどうでもいい雑音は気にしないもの。
まだまだ、本気が足らないと反省の日々。不景気なんか関係ない。どんな時代も己次第。
目線大丈夫?
気が付けば、いつも自分中心の「上から目線」になってはいないか。常に相手から自分はどう見られているか、わが商品はお客様から見たらどうなんだ。と相手の目線で見る癖をつけておきたい。「目は口ほどにモノをいう」。目線が変われば、言葉も行動も変わるはず。
そうすれば、ビジネスも人生もうまくいくはず。
初対面の全力投球
初めて会った人にどこまでパワーを発揮しているだろう?なんとなく名刺を渡して、なんとなく会話をして、その日が過ぎれば顔も名前も忘れてしまう?そんなことではもったいない。どこまで相手に印象付けることができるかが、その後のつきあいにも大きく影響する。一生懸命に接していると相手に残る。力を抜けば伝わり方もそれなり。
一度会って、相手から「また会いたい」と思わせたら、本望。これは営業の基本。
1通の手紙
電子メールがあまりに便利なため、手紙を書く回数が減っている。しかし、ここぞという相手、ここぞという時には、手にとって目で文字を追いかけてほしい。手紙とは着いたときのサプライズ感、開封するときのわくわく感。そして実際に文字が目に飛び込んでくるときの興奮。そして読み進めるにつれ、安堵したり、冷や汗をかいたり。手紙とはやはり、手に紙なのである。もしかしたら、相手の思いをしっかりと伝えてくれる「手の神」なのかもしれない。
自分の価値を高める
周りが焦ったり、不安になっている時期こそ、しっかり自己を見つめなおし、誰にもどこにも、どんな場面にも崩壊しない強い自分を創っておきたい。どんな時代にも価値があるものは売れる。価値があれば生き残れる。自分の価値とは何か?まさに自分マーケティングの時代である。使い捨てにならない、長く登用される人材であらねばならないし、パートナーでなければならない。今一度、この時代だからこそ、売れる自分づくりを。
厳しい時代って?
「大変な時代が来ましたね」と全国どこでも聞こえてくるこのフレーズに、「もうその挨拶はやめにしませんか」といいたい今日。大変は大きな変化。大きく変わるのが怖い?でも、世界は毎日変化しているし、厳しい厳しいというけれど、そんなに優しい道を来たのですか?と問いたくなる。誰にも言われなくても、自ら厳しい道を課し、努力をしている人も多く存在する。そんな人は世の中がどうであれ、わが道を進むだけ。
危機の時代とは、クライシス&チャンスの意味である。どちらを味方につけるかは、やはり自分次第。この時代だからこそ、がんばれる。自分に負けないことが肝心だ。
「ゲルマン精神」よ永遠に。
20年前、哲学入門していた頃、この精神が好きだった。日本人と根本的に気質が共通しているとも言われてきたドイツ精神。しかし、戦後、かなり両者は違ってきているように感じる。哲学も文学も音楽も・・。とくにアンビジュアルな精神世界の創造に対し、ドイツ人は天才的な才能をもっていると思う。いつの時代になっても古典は滅びず、グローバルスタンダードなる考えに動されることなく、わが道をいく誇り高きゲルマン。
ヘーゲルも、ゲーテもベートーベンもブラームスもカントもニーチェも・・。
現代人の内面に役立つ素晴らしい作品・思想を残した素晴らしい先人たち。
一番好きなドイツ語は今も「AUFHEBEN」(アウフヘーベン)。止揚と訳すらしい。常に発展に成長に向かって上昇し続ける。この精神性を今、今一度、学びなおしたい。
「続ける」ことは素晴らしい。
夢の実現とは、それに向けての行動を続けること。大きなことでなくてよいから、とにかく、それを続けること。勉強でも仕事でもダイエットでも。こうと決めたら、続けられると面白くなる、効果も上がる。しかし、三日坊主という言葉があるように、何かを初め続けることは人間にとってたやすいことではないようだ。ある一定期間がんばれば、自然とそれが習慣になる。そうやって人は成長していける。人から言われてルールに従うのはある意味簡単。見られていると、人は動く。しかし、夢に近づきたいならば、人に言われたことだけやっているわけにはいかない。だから新たな行動を自分ではじめる。そして続ける。誰も見ていなくてもコツコツ努力した人は必ず、幸せになれる。
