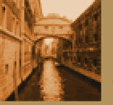


�`2006�N12��

�u�����邱�Ɓv���l���E�d��
���ǂ���Ƃ̖쑺��������B�u�l���͈������B60�߂��ĉ��߂Ă����v���v�BNY�ݏZ�̎��YUKA����B�u�E�T�M���T���Ƃ���ꂽ��A���̐l���͋T�ł��B�ł��邱�Ƃ����ł��Ȃ�����ǁA���������Ă�����E�T�M��ǂ��z���邱�Ƃ����邩������Ȃ��v�B���̂���l�̌��t�͐S�ɟ��݂�B��������Ƃ����Ȃ��Ƃ��A����͑債�����Ƃł͂Ȃ��B�����n������l���͊y�����B�������y�����R�g����͑����Ȃ��B�ǂ�Ȃ��Ƃ����낤�Ƃ��A�u��������v�u�s����������v���Ƃ��K�v���B����́u�����悤�Ƃ����w�C�́x�v�ɐs����B
�ǂ�ȏ����Ȃ��Ƃł��悢�A�������瑱�����邱�Ƃ��͂��߂悤�B����������Â��₵�Ă����A�u�v���Ă��鎩���v�ɋ߂Â���E�E�B
1���̃|�[�g���[�g��p�ӂ���@�@�`�i���Ɍ����鎄�̂��߂Ɂ`
�ŋ߁A�����̍ō��̃|�[�g���[�g���ӎ�����悤�ɂȂ����B
�����ɂ������̂��Ƃ��������Ƃ��ɂ��A����1���������Ăق����Ǝv���ʐ^���A�����ŗp�ӂ��Ă��������Ǝv���悤�ɂȂ����̂��B
���E�̔��p�قɍs���ƁA���܂��܂Ȑl���̏ё����ڂɂ��邪�A�ނ�͂����Ɖi���Ɏc�鎩�����㐢�Ɏc�������āA��ƂɋM�d��1����`�����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����Ƃ������݂͂��ʂĂ邩����Ȃ����A���Ȃ��Ƃ�����1��������Ύ����̂��Ƃ��v���o���Ă��炦�邩���E�E�B����͔߂������Ƃł͂Ȃ��A�y�����v���o�Ƃ��邽�߂ɑ�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��B
���̎ʐ^��V�����p�X�|�[�g�Ɏg���Ă݂��B�����A�V�J�S�̓��ǂŁu�����ʐ^���˂��`Oh!Nice~�v�ƖJ�߂�ꂽ�B
�u���E�h�~�v�͍L���ŁH
������A���E�������Ă���B�q�ǂ�����l���l���ɔ��āA������͂������Ď���I�ԁB�l���̈Ӗ����킩��Ȃ��Ȃ�A������͂��Ȃ��Ȃ�A���͂�������F�߂Ȃ��Ȃ�B���̂R�����E������ꍇ�̑傫�ȗv���ł���Ƃ����Ă���B�u�ǐl�v�������Ă���NIPPON�B�q�ǂ������͂܂��l����̌����Ă��Ȃ��������瑁�����鎀��I�ԁB�u�˂��A�������������āB�����Ă���Ȃ��Ɖ����Ɏ��E�����v�Ƃ̃��b�Z�[�W�𑗂�A���͂̑�l�����͋����A�E����������B�L�����g���āA�q�ǂ������Ɏ��E�h�~�̃��b�Z�[�W���`������B�G�C�Y�o�ŁA�A���K���h�~�E�E�E�A�����J�ł͍L�����g���A���܂��܂ȎЉ���ɑ��A�l�X�����S�����邽�߂̃��b�Z�[�W�M���Ă���B
�L���Ŏ��E���Ƃ߂��邩�H���������ɂ͂Ȃ��Ă������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����ł���͎̂��͂̋����Ɨ�܂��B�u�ꏏ�ɐ����Ă���v�����Ɛ������т̋��L�B
���͂Ɍǐl�����Ȃ����ƂƁA���������邱�Ƃ̈Ӗ���`���Ă������炪�{���ɕK�v�Ȏ���B�L���ł͂Ȃ��A����ł��ׂ����ƁB�L���łȂ��A����ł����ł��Ȃ����ƁB���ꂪ�u�l�Â���v�̂͂��B
�p�������̂�����Ȃ�
�����R�g������Ƃ��ɂ́A�����C���[�W���v���`���A�̂��ށB
�������A���̂Ƃ���ɂ����Ƃ�����Ȃ��B�u�z��O�v�̎��Ԃ����肤��B
�l�ԁA�����Ă����炢���ȏ�ʂɑ�������B�p���������Ƃ�����B
�N�����ł���Βp�����������Ȃ����A���������Ă��܂��Ă��S�z�͂���Ȃ��B
�p�Ƃ������͐S�Ɏ��Ə����B�S���q�ϓI�Ɂu�������Ƃ��ł���A�M�d�ȑ̌��Ȃ̂��v�Ǝv���悢�B�����ē������ƂɂȂ�Ȃ��悤�ɉ��߂Ă����悢�B
�p����������u��ϕ��ɂȂ�܂����v�Ƃ�����悤�ɂȂ肽���B
���K���x�E���K�����̃R�~���j�P�[�V����
�l�ԂƂ͎��̂��Ƃ��u�l�̊ԁv�Ə������A�l�̊Ԃ��A�l�ɊԂ��A�l�͊Ԃ��E�E
�����ȉ��߂��ł���Ǝv�����A������ɂ���u�ԁv�A�܂�l�͂ЂƂ�ł͐l�Ԃł͂Ȃ��A�W�̒��ł����������Ȃ��̂��l�ԁB�l�ԊW�Ȃ��̐l���Ƃ͂��肦�Ȃ��B�����œ�����́u�ԁv�B�ǂ��܂ŔM���ւ��悢�̂��A�ǂ��܂ŋ߂Â��悢�̂��B���N�͂��̂��Ƃɂ��đ�ϕ������Ă����������B
����Ƃ̉��K���x�E���K�����B������݂��邱�Ƃ��R�~���j�P�[�V�����ɂ͕s���B������������������łȂ��A����������ł��邱�ƁB
�Ȃ��Ȃ�������Ƃł���B���̎��H�̌��́u�Ί�v�ƌ������ł͂Ȃ����B
���_���E�ł̂��𗧂�
�e���̂Ƃ��A������s�@�ɏ�荇�킹�ꏏ�ɏ�������S����Ƃ͂���ȗ��̗F�l�B�Ȃ��Ȃ�����Ƃ��ł��Ȃ����A���_���E�ł̋��ʓ_�������Ă��邹�����A�قǂ悢�����̉��K�W�ɂ���B�v���Ԃ�ɉ�����Ƃ��A�ŋߓ��x�����Ƃ����B�������d���������Ă���̂ō݉Ƃ̗���ł̂��V����B
����Ǝ����̂��������Ƃ��ł���悤�ȋC�����Ă����B���̒��ō����Ă���l�̖��ɗ��Ă��炤�ꂵ���Ƃ����B�l���ꂼ��̐l���ɑ���v�������邪�����ł����̒��̖��ɗ��Ă���E�E�Ƃ����v���ƁA���̂��𗧂��̎d�������m�₨���łȂ��A���_�I�Ȃ��̂ł̂��𗧂��ł���Ƃ�������2�_�������̍l���Ƌ��ʂ��Ă���B�N�������Ō�͐S�̖��ɂ������B���̂Ƃ��ɁA�@���ł�����ȊO�ł������B�l�����C�ɂ��邱�Ƃ��ł���E�E�E�BS����Ɠ����v���Ŏ����Ⴄ���̂���Ă������ł��邵�A���ꂩ��������Ƃ����ƁE�E���̎v�����ɐ��������݂����B
�S�Ƒ��̎���
�������܂߂Ăł��邪�҂̑����A���q���A����E�E�E�l���\���̕ω��̒��A�u�Ƒ��v�̂���悤���ς���Ă���B
�Ƒ��Ƃ͉����B�l�Ԃ̈�Ԑg�߂ȎЉ�ł���A�l�����Ƃ��ɂ���^�������̂ł��낤���H
���ɂƂ��ẮA�݂��ɐl�Ƃ��đf���Ɍ������������Ƃ��ł���W�ł���A�S�ɏZ��ł��鑶�݂ł���A�����Ƃ����u�Ԃ���������W���B�����ɂ͌����E�����Ƃ����_��͂��܂�W�Ȃ��B�S�̉Ƒ��Ȃ̂ł���B
�����猻�݂͌Z���o�����������������B
���̐l�̂��Ƃ͂Ȃ����u�ǂ�ȂƂ������Nj�����v���A��������삯����B
�S�̎���B��������ʼnƑ��͑�Ƒ��ɂ��Ȃ��Ă����B�ł����̍��{�͈ˑ��ł͂Ȃ��A�����Ƒ��d�Ȃ̂ł���B
�������u���Ɖ���v�̋C������
���Ƃ��ANY����A�钩�̓Z���g�p�g���b�N����܂ŕ����Ă���2�h���̃L�����h�������āu�܂��������C�ɗ����܂��悤�Ɂv�ƋF���Ă���B��������Ȃ���A���Ɖ��邱�Ƃ��ł���̂��낤�Ƃ����v���B�H���������A���Ɖ�����������H�����Ƃ邱�Ƃ��ł��邩�Ǝv���B�Ƒ��Ƃ����Ɖ������Ƃ��ł���̂��Ǝv���B�u���Ɖ���v�̎v���́A1��̌o�����Ɏv���C�����A���͂ւ̊��ӂ̋C��������ށB�u���Ɖ���v�ɋ�̓I�Ȑ���������Ȃ��ł��������邱�Ƃ�S���肤�B
�n�[�����̃\�E���t�[�h�̕�@�V���r�A
NY�ւ������炢���C�ɂȂ��Ă������X�g�����B�n�[�����ɂ���\�E���t�[�h�̓X�B���N���C�ɂȂ��Ă������X�̂ЂƂB���������H�ו��͈ӊO��ӊO�A�퍷�ʎ҂̐������琶�܂����ƕ����Ă͂������A�n�[�����̃\�E���t�[�h�͂Ƃ��Ă������ł���B
�X�e�[�L���g�������D���ł͂Ȃ��B�ł������̃V���r�A�̃t���C�h�`�L������i�B���E���A�ǂ��̃}�}�������A�Ƒ��ɔ�������������H�ׂ��������Ǝv���͓̂����B�܂��Ɂu�}���}�̖��v�͉Ƒ��ւ̈���Ȃ̂��B�H�ނɂ����������Ȃ��Ƃ��A��Ԃ�������Δ�����������������B����Ȃ��Ƃ���������A�[�݂̂��闿���ŁA�Y�ꂪ�����B���̃V���r�A�ꂳ�Y����Ȃ��B���܂��܂ȕ��Q����������Ă��A�u������Γ��͊J����B���̂��ꂳ��ɂ܂���ɂ��������B�ꏏ�ɎB����1���̎ʐ^�����邽�тɉ��������v���n�[�����̂��̓X�B
�u�܂������v�����邽�߂Ɂu���Ȃ�v��
�u�܂������v�Ƃ����̂͏����ł���A�q��̂Ȃ���Ԃ��w���B
���̐l�́u�܂�����������v�B����͂قߌ��t�ł���B�������A�����l�����Ă��������ɁA�u�܂������v�̈Ӗ��𐳂����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ�B�c�͂܂��������悢�Ɍ��܂��Ă���B
�����炵���A�����̎v���𐋂���̂ɂӂ�ӂ炵�Ă͂����Ȃ��B
�������A�ǂ�ȂƂ����N�ɑ��Ă��u�܂������ł����Ă悢���v�Ƃ����A�����ł͂Ȃ��B�܂������Ȏv�������ɂ́A�Ȃ��Č�����A�܂�Č}���邱�Ƃ���Ȃ̂��B
���Ȃ₩�Ɂu���Ȃ�v�͂Ƃ����������B�����Ď����̈ӎv�����܂������߂ł͂Ȃ��A�����̐�������S�����邽�߂ɁA���ɂ͋|�̂悤�ɃL���[���Ƃ��Ȃ�͂��s�����B
�I���i�͌����A���Ȃ₩�ɁB���̏d�v�����킩��͂��߂��E�E�E�B
�u�C�v�����Ă̈Ӗ��́E�E�E
�ŋ߁A���̒��Ɂu�C�v�������Ȃ��l�������Ă���悤�Ɋ�����B
�u�C�v�Ƃ͉F���Ƃ̑Θb�E���a�B�����̏B���ɂ́u�C�v�͂Ȃ��̂�����B
���́u�C�v�����܂�ɂ����ڒ��ɂȂ��Ă���悤�ȍ����B
�C�������������邽�߂ɂ��A�����ĎЉ�ƂƂ��ɐ����邽�߂ɂ��ŏd�v�ȃG�������g�ł��邱�Ƃ��m�F�����������B
�u�C�������v�u�C�����v�u�C�ɂ�����v�����̍s���̂��тɂ��̂��Ƃ�S���������B�Ȃ��Ȃ�������A�ӎ����邱�ƂŌl�������̂������A�u�C�v�Ƃ͐�����p���[�Ȃ̂��B�u�C�Â��v�l�͐��E�������邵���̕������Ή����ł���B�d�����ł��邵�A�������[�����A�F�B��������͂��B�������u�C�v�ɖ������K���l��ڎw�������B
�R�R��������Ɛ[���Ȃ�A�傫���Ȃ�̎���
�S�Ƃ͂ǂ�ȃJ�^�`�����Ă���̂��낤���H�ǂ�ȑ傫���Ȃ낤���B
�ƍl�������Ƃ͂��邾�낤���B�����O���Ƃ̃V���b�N���N����ƁA�S�������A�������Ȃ�B�܂�Ȃ����Ƃł��悭�悵����A�l��������ł݂���B����ȂƂ��ɂ́A�S�Ɍ������Ęb��������u�����Ƒ傫���A�����Ɛ[���v����Ȏ�����������ƁA�����Ȃ��B�����ƐS�͐L�k���݂̊C�ȑ̂̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƒz�����Ă���B
�ǂ�ȂƂ����A�K���ȋC�����ł��邱�Ƃ���������B���̂��߂ɂ͏�Ƀ|�W�e�B�u�ȐS�ł��邱�Ƃ���B������A�h���Ƃ��������Ƃ��͎����������悤�B�u�R�R����R�R����R�R������E�E�E�[���A�L������v�ƁB
����Ȃ��Ƃ����肩�����A�����������琢�E���̖��������ۂݍ��߂�啨�ɂȂ�邩���E�E�E�B
��҂����̔M���@�����݂钇�ԂƂ��Ă̋����̗̂�
�Ј��̕��ϔN��Q�O��Ƃ�����Ђɂ��o������B�����ł̃C�x���g�B
�Ј������͎Ⴋ�В��i�R�W�j�̃V���{���ƕ`���A�����������́E�E�E
�̋C�����ł�����Ă���B��Ƃ̐����A�l�Â���́A�����ɂЂƂ�ЂƂ�̐l�Ԃ������������āA����Ɍ������Đi�߂邩�A���̊���ł��邩�ɂ������Ă���Ǝv���B�P�ɖڂ̑O�̏����̂悵�����ł͂Ȃ��A���̐�Ɂu�����Ȃ��v�u�����܂ł�����v�Ƃ�����̓I�ȖڕW�����邱�Ƃ�����B
����Ȋ��œ����Ј������͔M���I�Ɏd�������A�����ėV�ԁB�M���ł���͎̂Ⴓ�ł���B���̗͂��܂Ƃ܂����Ƃ��W�c�͂ƂĂ��Ȃ��p���[�Ƃ��ē����o���B�o�c�҂Ƃ����̂́@�Ј��ɖ����������Ă���邨��{�łȂ���Ȃ�Ȃ�
Where are you from? ������̈��A�́A�u�݂�ȗ]���ҁv�Ńr�b�O�ɂȂ�����
�A�����J�Ń^�N�V�[�ɏ��ƁA�K���������B���{����A�����������Ă����Ƃ����ƁA���ꂵ�����Ȋ�B�Ȃ����������痈�Ă���Ƃ����悻�҂ɑ��A�e�ߊ������̂��A�����J�̃��[�J�[�H�ނ���u�������n�C�`���痈���v�u�p�L�X�^�����v�����Ȃǂ́u�G�`�I�s�A����v�Ƃ����A�ꏏ�ɏ����B
���{�ł͂��̉�b�͂Ȃ��B�����āA�悻�҂����͉����c���E�̋��̂��Ƃ������������B�̋��̂��Ƃ������v���l�͂��Ȃ��B��Ȃ�n�Ȃ̂��B���̂Ƃ��A�������{�̂��Ƃ��ւ�������Č���Ă���B
���Ζʂ̃^�N�V�[�h���C�o�[�Ɓu�ւ��B����苛�������Ȃv�Ƃ�����b�����Ă��邱�Ǝ��̂����������āA���̏�Ȃ��y�����B
�����]���҂ł���B���̏ꏊ�ɁA��C�Ɋ��ꂷ���邱�ƂȂ��A�ْ����������Ďh���I�ɐ�����E�E�B����Ȑl���͂Ȃ��Ȃ��悢�Ǝv���B
���t�͎v���A�����ďd���B
�ŋߍu���Ȃǂł悭���t�̈Ӗ�����b�����Ƃ������B���C�Ȃ��g���Ă���
���t�ɂ��A���͑�ςȈӖ������߂��Ă��邱�Ƃ������B�����Ċ����Ƃ�
���낵���悭�l�����Ă���\�ӂ̋L���ł��邱�Ƃ����߂ĒɊ�����B
���Ƃ��u�l�v�Ƃ����ȒP�ȕ������Ƃ��Ă��������B�������A��������
������A�Ӗ����l���邱�Ƃ������A�ȒP�Ɍ��t���Ă���B
�{���Ɏv����`���邽�߂ɁA���̐[���ďd���Ӗ��������Ɨ������Ă��Ȃ����
�Ȃ�Ȃ��B
�������Ƃ��͎������������B���t�ɂ����s�p�肪���邪�A�^���͕ς��Ȃ��B
�������̈Ӗ���K���������A�`���������Ƃ��m���ɓ`���悤�B
���t�̃R�~���j�P�[�V�����͊ȒP�ł͂Ȃ��B�ꌾ�ꌾ���{���ɏd���̂��B
�N�ւ��ւ�ɂł���l����
����Љ���������鐢�̒��ɂȂ����B�����Ď������������������Ĉ������߂Â��Ă���B�R�O��㔼�C�ɂȂ�͂��߂������B���͂���ɂ����ꂽ�B
���͋ؓ��̂���݁AᰂƂ������ۂւ̏ł�B��������X�������葱���邱�Ƃւ̓w�͂͑ӂ炸�A�ł��邱�Ƃ͂���B�������Aᰂ����悤�ɂ���Ă͐l���̔N�ցB
�V���邱�Ƃ��X���ł���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B���������f�G�ł���A�������͓��ʂ�����Ă���͂��B�����̐�y���������Ă��Ă����v���B
�����ւ�����Ă鐶���������Ă���A���ꂢ�ɂȂ��B���ꂢ�ł��邱�Ƃ��ł���B����ς�l�ԁA���g�����B��������O������h������������^���ĐS�����X�ł��葱����悤�ɐ����Ă��������B
�������ɂ��鍑�C�^���A
3��8���́A���ׂĂ̏������j���E���ӂ������B�����ł́A�~���U�̉Ԃ������Ƀv���[���g���ꂽ��A�u�[�P�̌`�Ɍ����Ă��`���R��L�����f�B�[��������B�Ȃ�ƍ��S�ɏ���Ă����ׂĂ̏����ɑ����邻���ŁA�������������s�����B�����͂��Ƃ���ւł��Ԃ��ِ����瑡��ꂽ�爫���C�͂��Ȃ��B
���{�Ǝ��̃z���C�g�f�[�Ƃ͂�����Ǝ���Ⴄ�B�C�^���A�j�̓}���}���ɂ���Ƃ����B�f���炵���B�����{�łً͌ϖ@���Ƃ��A���邢�͈玙�x�ɂ��Ƃ��n�[�h�ʂł̎Љ�Ŋ������鏗���ւ̃n�[�h�ʂł̃T�|�[�g�͐i��ł������A�����Ɗ�{�I�Ȃ��ƁB�u�����Ɋ��ӂ���v�Ƃ������Ƃ����R�ɂł���悤�ɂȂ�E�E�E����������j���Ɋ��ӂł���B���݂���F�߁A���d���A���ӂ���B����Ȃ��Ƃ��ł���E�E���Ƃ��܂���ł͂Ȃ����B�C�^���A�͂��ׂăX���[�ł��邪�A�����ɂ͖{����������Ă���B
��̐��������邱�Ƃ��K��
�����K�����B�����������ς��҂����ƁH���������̂��Ȃ邱�ƁH���h�ȉƂɏZ�ނ��ƁH�u�����h�i��g�ɂ��邱�ƁH�������X�g�����ɍs���邱�ƁH
�ŋ߁A��ԍK����������̂́A��т𐆂��ĐH�ׂ�Ƃ��A�U�������Ă���Ƃ��A�����ĉƑ������C�ł��邱�Ƃ��m�F�����Ƃ��A�����ċ����ݓn���Ă���Ƃ��E�E�E�B������������邱�Ƃ��K���B�g�т���ɁA�p�\�R������ɖڂ������āA�����̓V�C�ɋC�Â��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����H
���A���C�ɁA���N�ɐ����Ă��邱�Ƃ������邱�Ƃ���������������ȂƎv���Ă�����A�X�[�b�Ɨ]�v�ȓł��͂������Ă���܂��K���B
�m�x�ɗ��������q
�N�ɉ��x���ʂ����Ƃ��ł��Ȃ��̂ɁA�����o�[�ɂȂ��Ă��郁�g���|���^�����p�فB���x�A�Ȃ����D�悵�Č��Ă��܂��̂́A���Ă̍�i�B���������A�����J�֗����̂�����Ȃ����������Ă��܂��B�������I���̍L��ȕ~�n�̒��ɃA�W�A�ق�����A���̂Ȃ��ɑf���炵�����{�ق����邱�Ƃ��A�Ȃ�ƂP�T�N�ڂɂ��ď��߂Ēm�����B����ȕ�������A���@����܂ŁB���`���Ԃ̛����悩��A�����k�ւ܂ŁE�E�E�܂��ɓ��{�̂Q�O�O�O�N�̔��p�j�����Ղł���R���N�V�����ł���B�悭�C��n���Ă���Ă������B�����ɂȂ�Ƃo�q�n�m�b�d�@�r�g�n�s�n�j�t�̑����I���{�ł��ŋߌ��Ȃ��Ȃ����������q�������Ă���̂��B
���{�l�Ƃ��āA�����Ɠ��{������Ȃ���Ǝv�����Ɠ����ɁA���̂m�x��p���Ȃnj|�p�̍����I��i���ɂ����āA���{�̕�����������Ɠ`�����Ă��邱�ƂɊ������A�܂��ւ�Ɏv�����B
���{�l�͂�͂胂�m�Â���̖����̏W�܂�ł���B�܂��@�ׂ͕\���������������ł���B���{�����̓����́u���ȁv���ƁA���g���|���^���̐����ɂ������B
���{�݂̂Ȃ���A�u���ȁv�������Ƒ�ɁB�Ƃ����Ă���悤�������B
�������͔N�ɏo��
���g���|���^�����p�ق́A�{�����e�B�A�Ɗ�t�ʼn^�c����Ă���B���̑�D���ȃ~���[�W�A���V���b�v�ł��V��j���̃{�����e�B�A���ڋq������B
�����C�ɂȂ��Ă����̂́A��������X�^�b�t�B���ꂪ�f�G�Ȑl����Ȃ̂��I�����Ƃ��̕��͎Ⴂ�Ƃ�������p�ق��D���������B�Ƃ����{���肻���Ȑl���ȂƂ��E�E�E�Ƃɂ������̐l���̂����p�قƂ��������̗��j������������l�����X����̂��I����������B�����T���������Ă���ƁA���J�ɒ��J�ɐڋq�����Ă��ꂽ�V�O���炢�̕��B�ޏ����r���ŐȂ��͂��������ƁA����Ɍ��C�Ȏ�҂��Ή����Ă��ꂽ�B��������e�ł͂��邪�A��҂̐ڋq�ɂ͐[�݂��Ȃ��A���������u�r�n�@�o�q�d�s�s�x�v�Ƃ��P�������āA���܂芴�����Ȃ��B�i�����Ƃ��������̌�w�͂����̒��x�Ȃ̂ŁE�E�E��������Ȃ��j�i��߂����A��v�����Ă���Ԃɂ��̔N�y�̕��͖߂�A�Ⴂ�l�̐ڋq���ז����邱�ƂȂ��A�Â��ɉ��������ɂ��̋�C��ǂݎ���Ă���ꂽ�B
�A��ہA���͂��̂�������ɁA�u���Ȃ��h���܂��B�������Ȃ��̂悤�ɂȂ肽���ł��B�p�[�t�F�N�g�ȃT�[�r�X�ł����B���肪�Ƃ��v�Ƃ�������A��������͊������ɂ����Ⴍ����ɂ��Ċ��ł����������B�������͈���������B�l�͔N���Ƃ�A�N�ւ�������B�������͔N�ɏo��B�ǂ�Ȃ����l���𑗂��Ă��������A��ɔw���ɏo��B�������V�k��ڎw���܂��B
�E�Ƃ���Ȃ��u�������v�Ȃ@
�P�O�ォ��N�Ƃ��Ă����ƎВ��Ƃ����A���؈ꕔ����ƍŔN���̎В��Ƃ̉�b�B�u����͂����E�Ƃ���Ȃ��A���̐��������̂��̂ȂB�����炱�̎d�����ے肳���Ύ������g��ے肳��Ă��܂��Ƃ����C�����ł����S�͂Ő����Ă���v
���̌��t�ɑ�ϋ�������B�������B�d���̓��e�͈Ⴆ�ǂ��A���������̎d���͐E�Ƃł͂Ȃ��u�������v�ł���Ǝ������邱�Ƃ�����B������n�m���n�e�e���Ȃ��B���������ɂ����Ȃ��Ƃ��y���݂Ȃ��猩�����A�l���A�s������B�ꌩ�V��ł��Ă��d���̂��Ƃ��l���A��������N���A�C�f�A�͖����ł���A�d��������ɂ����������J���A����܂łɂȂ����̂�n���Ă����B���ꂪ���̐�����������B�����A�ЂƂ̎d���ɐ�O���Ă�������ɂ��Ă���ނƁA�����Ȃ��Ƃɂ�����������o�������Ƃ͂�����ƈႤ��������Ȃ��B���͎d���ɐl����q���A���̒��őf�G�ɐ������A���h�Ŗ��͓I�Ȑl�ɐi������ނ������Ɖ��������������B���̐l���r�b�O�J���p�j�[�̎В�������łȂ��A�ꐶ���������Ă���l������E�E�E�ł���B
�l���鑒�V�r�W�l�X
�̐��E�ł͊ȒP�ɐl�����ʁB���܂�������Ȃ��B�g�߂Ȑl�̎��͂����z�����邾���ł��|���B�����̎��͂܂��Ă͑z�����ł��Ȃ��ł���B�ŋ߂͍���Љ�ŁA���V�r�W�l�X���i���Ɣ��W�𐋂��Ă���B����������ɁA�m����o�����Ȃ��Ƃ��X���[�Y�Ɏ���s�����Ƃ��ł���B�q���̂���ɖڂɂ������V�̏�ƍ����̂���́A�������Ⴄ�B
�������l�����ʂƂ������Ƃɑ����̋C�����͕ς�邱�Ƃ��Ȃ����A�������̎������قƂ�NJ����邱�ƂȂ������Ă��܂��B�ǂ�������e���r�h���}�̃����V�[���ɂ���悤�Ȋ����ł���B
���ꂩ�獂��Љ�ɂȂ�A�����̎��͂ɂ����N��肪�����A�g�߂Ȑl�������Ă��܂��@��������邪�A���̂��ƂɊ�����������̂ł��낤���B����A����Ȃ͂��͂Ȃ��B
�����Ƃ����Ƃ��قǗ����l������̂͂��肪�������ƁB�����炱�̃r�W�l�X�͂܂��܂����v�����܂�B����ɂ��Ă����̋ƊE�͐i�����Ă���B���ɂ̃z�X�s�^���e�B�Y�Ƃł���B
�J�Ǝ��ɂ͂����߂��L�����y�[���̂悤�Ȋ�������ƕ����A�����͎̂��������낤���B
�����Ȃ鎥�C�@�キ�Ȃ��Ă������C
�ŏ��o��B���̐l�Ƃ͍����Ȃ��Ƃ��A���܂��܂ȋ����������Ă��̂��������͂��܂�B
���̐l�Ƃ����Ƃ������Ă����邩�A�����ł͂Ȃ����E�E�E�E�B��ώc�O�Ȃ��炷�ׂĂ̐l�Əo����������瓯�����q�Œ��N�������Ă������Ƃ͕s�\�ł���B�P�N���߂���ƐV���ɏo������l�A������Ă����l�E�E�E���낢��ł���B���܂����o��̂Ȃ��Ŗ����Ƃ����y�[�W���߂����Ă���ƁA�ǂ����Ő������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�B
�����������Ԃ̒����͊W�Ȃ��B���������炵���A���������R�̂Őڂ��Ă����邩�B
�����ċC�����������E�E�E���ꂪ���C�̋�������߂Ă���B
�C���������l�ƒ�����������Έ�ԍK���B����ȏo����ǂꂾ���a����̂��낤�B
��������ĕ�����
��D���ȋȂ̂ЂƂB��{��Ƃ����V���K�[�͖{���Ɉ̑�ł������B���{�l�ɗE�C�Ɗ�]��^���Ă��ꂽ�B���̑��Ɂu���グ�Ă�����̐����v�����ȁB������������Đ����邱�Ƃ������Ă���Ă���B�����̋Ȃ��������݂Ȃ��璬������B�������A������������čs�����B���̊Ԃɂ��w�̓s���Ƃ��Đ����Ă��鎩���Ɍւ�����Ă�C�����Ă���B
�m�x�̃R���T�[�g�̃I�[�f�B�V�����v���O�����ɂ�������荞�B
�����A���E�̕���ŏ�������ĉ̂��������ȁB�r�t�j�h�x�`�j�h�@�r�n�m�f�Ƃ����^�C�g�������������B�ł��@�r�g�`�a�t�r�g�`�a�t�@�r�n�m�f�łȂ��Ă悩�����B
�Ƃ���ŁA�ŋ߂͂R�U�T���̃}�[�`���f���炵���Ǝv���B���̎���A�O�����E���C�Â���̉̂����{�����C�ɂ��Ă�����ł��ˁB
��������͌��t�ɂȂ�Ȃ����ӂ̂��邵
�����e�����l�Əo��ƈ��������B����̉��x���m�F���A�M���W�Ŋ����邽�߁B
���������肾�Ƃ�����B�Ԃ�����Ƃ�����B���̊Ԃɂ�������ƈ���Ȃ����Ă���B
����A�e�����l�̍Ŋ��̂��ʂ�́A��������Œ��߂�����ꂽ�B���̐l�́A��サ���Ȃ�����ň����Ă���Ƃ������͂����G��Ă���Ƃ��������Ŏ��̎�𗣂��Ȃ������B
�u���肪�Ƃ��A���肪�Ƃ��v�B�Ȃ������ӂ̌��t�ƈ���͂悭�������B�͐s����܂Ō��킵�����A�̂悤�������B
���̗]�C�c��キ�������肪�Ŋ��̈��A�ƒm�����̂͐�����ł������B
������������Ă��A���ꂪ�Ŋ��̂��ʂ�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁE�E�E�E�B
���ł����̎�サ�����G����Ɏc���Ă���B
�����͏o�������A��������A����l�ł������B���ꂪ�����p���[�̔��M�Ǝv������B
�������̂Ƃ���
���N�@�⌾�������˂Ǝv���A�����Ȃ��ō��N�����Ă����B�l�͖���̂Ƃ��͂Ȃ��A�킪�g�ɂ͊W�Ȃ��Ƃǂ����Ŏv���Ă���B
�������A��s�@�ɏ������A���m��ʏꏊ�֏o�������Ƃ����������@�����Đ��E�ɂ͊댯�������ς��E�E�E�B
�������̂Ƃ��́A�g���Â��̃p�X�|�[�g�Ɠ��挔�̐�[�A�x�[�g�[�x���̊y�������ɓ���āA�D���Ȓ��̒n�}�ƎB�����ϗ��Ԃ�p���̊X�p�̎ʐ^���ꏏ�ɂˁB
���Ƒ��V�͂���Ȃ��B��������Ȃ��̂ŁA�Â��ɑ����Ăق����B���̂��Ƃ́E�E�E�E
����ς肫����Ə����Ă������B����̂Ƃ��̂��Ƃ��A���������Ȃ��Ƃ��̂��Ƃ�z������̂͂������ȍs�ׂł���B
�ł��A�{���̂������̂Ƃ��́A�����B���ꂵ���Ȃ��B����Ȑ��̒��ɂ����ẮB����܂ł������B
�Ⴄ����I
�l�Ƃ������Ƃ��A���҂��������Ȃ������悢�B�������Ă���l���狳�����邱�Ƃ̂ЂƂB�����������Ȑl�Ƃ̂������ŁA�l�͎����ƈႤ�Ƃ������Ƃ��O��ɂ��ׂĂ��l���邱�Ƃ̑����Ɋ�����B
����̈Ⴂ�A���܂ꂽ���̈Ⴂ�A�@���̈Ⴂ�A�����Ȍo���̈Ⴂ�E�E�E�����Ɠ��������A���l�����l�͂܂����Ȃ��B�����Ď����̂��ꂪ�������Ƃ͌���Ȃ��B
������A����ē�����O������A���ׂĂ�������X�^�[�g����̂����傤�ǂ����B
�Ⴄ����E�E�E�Ǝv���Ă��āA�������ʓ_���݂���Ƃ��ꂵ�����A���҂��Ȃ��ʼn������ꂵ�����Ƃ�����A���̊����͂ЂƂ����B
���҂��Ȃ��B����͈����Ӗ��ł͂Ȃ��B
���������Ȃ��A���������Ȃ��Ƃ������R�s�[�����������A�l�ԊW�̃o�����X�悢�����������A��������Ȃ�Ȃ����ȁB
�܂��A�Ⴄ�Ǝv�����ƂŁA�w�ׂ邱�Ƃ͖�����B
�قǂ悢���������A�����ɂȂ�B
���ł�����Ⴍ�@���ꂪ�ł��Ȃ���c�Ƃ���Ȃ�
�ǂ�ȂɎЉ�I�n�ʂ��オ���Ă����Ă��A��ɍ��̒Ⴂ�l������B�܂��l����ɓ��������邱�Ƃ��ł���l������B����ł����c�ƁI�Ƃ����v���Ă���B
����Ȃɕ��G�Ȏv���ł����Ă��A���Ƃ��قȂ�v���ł����Ă��A�₦���Ί�ő���ɓ�����������B�����̓s���ł͂Ȃ��A����̗���ɂȂ��ĎӍ߂���A���s�����B
���肪��ԂȂ����ł����̂ł͂Ȃ����B�ېg����n�܂�Ƒ���͊�Ȃ��B
�K�͂��傫���낤���������낤���A����̗���ɂ܂��Ȃ�邱�ƁB���ꂪ�}�[�P�e�B���O�̊�{�ł͂Ȃ����ƍŋߎv���ĂȂ�Ȃ��B
����������Ƃ́A�����������Ƃ������ƁB��������{���̃j�[�Y��������̂�����B
�ꊇ��ɂ���̂͂ǂ����H�������ォ��v���A�}�[�P�e�B���O�̌��_
�Q�O�O�V�N���Ƃ��A�c��̒�N����Ƃ��悭�����邪�A������Ƃ����āA�����������ꊇ��ɂł���Ƃ������Ƃ͂Ȃ��B���܂��ܓ������ɐ������Ƃ��������łǂ�Ȑl�������ł��āA���ꂩ��ǂ����������͐獷���ʁB
�����Ă݂�����l�������̂����̎���̎Y���Ȃ̂�������Ȃ����B
�}�[�P�e�B���O�R�~���j�P�[�V�����̐��E�������Ɖ��ڂŌ��Ȃ���A���E�����߂����Ă����Ȑl�ɏo����Ă��邤���ɁA�l�͂����Ȋ�������ł��邪�A����͈��������̕��ނł����Ȃ��A���͂��̐l�ɂƂ��čł���Ȃ��܂��܂ȑ��������Ă����肷�邱�Ƃ�����A���Â��^�[�Q�b�g�ݒ�Ƃ͓�����̂��Ǝv����B
�l�͐��܂ꂽ���ԁA���ʁA�ꏊ�A���j�A���A�W�A�o�ϊ��A����A�@���Ȃǂɂ��܂������Ⴄ�v�l�������A�Ⴄ�n�D�����悤�ɂȂ�̂ł���B
������x�A�{���̃}�[�P�e�B���O���l�����������ɗ��Ă���̂ł́B
�N�w�́u�悭�l���邱�Ɓv
�w������B�N�w��U�Ƃ����̂������������E�E�E�������ꂾ���ŁE�E�E����ȓN�w����{�I�ɕ��ׂĂ����Q�O��B�Љ�l�o�����ΐl�o�����Ȃ��w���̃u���U�C�ɁA�J���g��f�J���g���킩��킯�Ȃ��B�������炱���A�]�v�����v���B
�w�[�Q���̗��j�N�w�͗��j�Ƃ͔��W����Ƃ����l�������ʔ����������A���ꎩ�́A�Ȃ��w�[�Q����������l���������Ƃ��ł������A�͂��܂��A�N�w�ƂƂ����̂͐E�ƂŃv���̓N�w�ƂƂ������̂��Ƃ��v���Ύv���قǁ@�����Ɉł̒��E�E�E�E�E�B
�������A���������܂ł����ƓN�w�̎��ӂ�������Ă������Ԃ���������A���y�ɏ���������������Ă����������ŁA�u�l���邱�ƁA�����邱�Ɓv�͍D���ɂȂ����B
�����āA���������ł���A��������̎d�����D���Ȃ̂ł��낤�B
�����āA���ł́u�悭�l���邱�Ɓv�̑����Ɋ�����B�����āA�ꌩ������O�ɂ݂��邱�Ƃɑ��u�Ȃ��Ȃ낤�v�Ƃ����ڂ������Ƃ������ɑ���������Â킩���Ă����B�r�c���q����Ƃ����N�w�Ƃ̕����A�N�w�Ƃ͂����������Ƃ��Ə����Ă���ꂽ�̂��A�ƂĂ����ꂵ���v�����B�i�܁A������͒ꂪ�̂ŁA�p�����������j�悭�l����Ƃ������Ƃ́A�����Ȍ��ۂ����߂Ȃ�������
�₢�������Ƃł���A����ׂ��p�����₷�邱�Ƃł���B�����Ƃ͉����B���̂��߂ɐ����Ă���̂��B�����炭�N�w�̏I���_�͎��Ɍ������������ǂ邱�Ƃł͂Ȃ����Ǝv�����A����͂��Ȃ킿�����邱�Ƃւ̖͍��ł���B
�N�w�͓�����Ƃł͂Ȃ��Ȃ����B�����Ă���ȏ�Y��Ă͂����Ȃ���ȐS��
���̓����ł���B������f�J���g�́@�R�M�g�@�G���S�@�X���@�Ƃ������̂ł͂Ȃ����B
�����l���邱�Ƃ����Ȃ���A����͎����g�ł͂Ȃ��̂��B
�����Ă���ȏ�A���ł��葱�������B������A�悭�l���Đ��������B�܂��l����
����Ȃ����������߂�
Sep,2005
���̍d��
�u���̐l�͓����d����`�v�Ƃ͂悭�������A��p�̗F�l�ɕ����ƁA�瑊�w�ɂ��ƁA�����d���l�́A��ł������B�l�̘b���Ȃ��ƁA�ǂ�ǂ�d���Ȃ�̂��A���Ƃ��ƍd���̂ŁA�����Ȃ��ƂɎ���݂��Ȃ��̂��E�E�B
�F�l�͎��̎��ɐG���āu����A�܂��܂��d���ˁv�ƂԂ₢���B
��������̂��l��
�l�Ԃɂ͂����Ȋ炪����A���X�A���̐l�̈ӊO�Ȗʂɋ������肷�邱�Ƃ�����B���Ď����ɂ͂����̊炪����̂��낤���B
����F�l�͂S���Ƃ������B���̊���g�������Ă��邩��A�����̃o�����X���Ƃ��̂��Ƃ����B�����Ă��̊�ł��̏�ʏ�ʂ������Ă���̂��Ƃ����B
�������A�l�Ԑ��͂��̑��ʐ����ʔ����̂�������Ȃ��B���āA�����ɂ͂����̊炪���邩�B�����ĉ�����Ƃ͈ӎ����Đ�����Ƃ������ƁB�p���[�����\�K�v������ǂ��A�������閞�����𖡂���Ă݂����C������B
�X3�Ό����В���
�q�[�@�����@�A���܁B����������ƁA����܂���B�e���r�Ŕq�����������ł��B�u�d���̏�ɋ��͂Ȃ��B�d���̉��ɋ�������v�u�l�E���m�@�������E���������E�}�����v���̂����t�����̂܂܂X�R�N�̐l���Ŏ��H����Ă������ł��B
�p�\�R���Ȃ��A�����͎�n���A����̕ω��ɑΉ����Ă���r�Y�@�X�^�C���Ƃ͂����Ȃ���
��������J�b�R�����d�����܁A�����l�ł���B
��͎Ќ��_���X�ƁA����܂��������B���܂ł������C�ł����������B�l�Ԃ͎��ʂ܂Ő����ł�����̂��Ƌ����Ă��������܂����B�����A��ɖK�˂Ă��������ł��B
�C��炸�A���炸�A���R�́B�̂��l�قǁA�{���ɂ����Ȃ�ł��B
���߂ċ������܂����B�����܂ł������C�ŁB�S����̑��h�����߂āB
�V���ɍڂ�Ƃ�������
�������g�̂��Ƃ��V���ɏo��Ƃ����̂́A�ǂ����C�p�����������̂��B�ڂ���e�͑債�����Ƃ��Ȃ��Ƃ��A������݂������̐l����A�u�����̂��Ƃ̂悤�Ɋ������v�u�ւ炵���v���v�Ƃ��A�S���\�z�O�̔���������ƁA�}�X�R�~�ɏo��Ƃ������Ƃ́A�������ƂȂ̂��Ə��߂Ď��������B�Ƒ����V���ɍڂ�Ƃ����o����m��Ȃ��䂪�Ƃł́A�u�M�͂�������݂�����Ȃ��v�Ƃ��������B���߂āA���͂̕��Ɋ��ӂ̈ꌾ�ɐs����B
���獢��l
�ŋ߁A�����ɂƂ��Ď�������ɖS���Ȃ��Ă͍���l���ӂƐ����邱�Ƃ�����B
���̐l�����́A�����̐S���ł���A�����̐��ł���B
�Ȃ��A�����v���̂��A�D���Ȑl�������ǂ�ǂ�ɂȂ��Ă������炩����ɔ����A�������N���Ƃ��Ă����B�����̑�Ȑl�ɂƂ��āu���獢��l�v��
������悤�A���X���i�������B
�ЂƂ�̌��E���@���E��
�g�D�ɑ����Ă��Ȃ�����A�g�D�Ő����Ă��Ȃ�����A�u�ЂƂ�̗͂͂������m��Ă��܂���v�Ƃ����āA��������������Ƃ��������B���̌��E�ɒ��킵�āA���̌��t���o��Ȃ�悢����ǁA���E���m��Ȃ��ł���Ȃ��Ƃ킩��̂��ȁB
���E�ɂ͂ǂ�ǂ킵�����A�����̋��E�����L�������B���E�������E�����ς�����͂��B�Ǝv���Ă������A�N�����Ă���ʐl�̂P�O�O�O�{���̒��ɍv�����Ă�����ƍ���b���Ă�����A�u�l�����������Ƃ́A���ׂĂ͂ł��Ȃ��ł���B��͂��l�ɂł��邱�Ƃ͌��E������܂��ˁv�������܂����B���̕��̖��́A���E���e�������悤�ŁE�E�E�B
�s�������z����C�}�W�l�[�V������
�����Ă���ȏ�A�s����Ȃ��́B�Ȃ����@��ԑ�Ȃ��܂Ő����Ă����邩���킩��Ȃ��킯������B�l�Ԃ͋�̓I�Ȏ��ۂɊւ���u�S�z�v�����A�����ƒ��ۓI�Ŕ��R�Ƃ����u�s���v�Ƃ������݂ɂƂ����A�ŋ߂ł͐��_��a�ސl�������Ă���B
���肵�Ă���̂����ʁA���S���S����{�Ǝv���Ă��邩��s��������Ȃ̂ł����āA�ŏ�����s���ł���E�E�E�Ǝv���Ă��܂��A�����|�����̂͂Ȃ��B
�ق�Ƃ��ɕs���Ȃ��Ƃ͂Ȃ����Ƃ����ΉR�ł���B�����͎d�����Ȃ��Ȃ�Ȃ����A�a�C�ɂȂ�Ȃ����A�D���Ȑl������ł��܂����肵�Ȃ����E�E�E�B�������A�l���Ă��Ă��ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��B��ɂ���Ȗ���̂��Ƃ�z�����Ȃ���A�S�̔��������A���͂����Ȃ��Ă��Ȃ��Ƃ��������Ɋ��ӂ��āA�y���������Ă������B
�s�����A�s�����Ƃ����Ă��邾���ł͉��̉����ɂ��Ȃ�Ȃ�
�����ɖO���Ă���
�����@���m���@�R�g�������ς����B�������Ă���Ƃ������́A�]���Ă���B�Ȃ�����Ȃɂ����ς����m������Ă��܂��̂��H
�Ȃ�����Ȃɂǂ�ǂ�V���i���o����������̂��H�������̂��ǂ��ł������ł�����̂��H���������܂ŁA�u���肪�����v�̋C������A�u���ꂪ�ق����v�̗~���͎�����B�����A�X�g���X�����ɁA�C���]���Ƀ��m�⎞�Ԃ�����Ă���悤�ȋC������B
�����ɖO���Ă���B�����ʂ��킩��Ȃ��̂ɁA�O���Ă͂����Ȃ��B
�O���Ȃ�����n���Ă������Ƃ����炪�K���ɂȂ��i�ł���Ǝv���B
�܂̔���
��p�̎�҂͏�C�ɏo�Ă����l�������Ă���A��p�Ɏc��l�X�Ƃ�
�ӎ��̃M���b�v�����܂�Ă���B����͂����ƐA���n�Ƃ��đ����Ă���
���̍��̏h���ł��ˁB����̖��ł��ˁB�����Ɏ����̍��Ɉ���ƈ����ƌւ�����l�Ԃ𑝂₵�Ă����邩�B���ꂪ���̍��ɂƂ��Ă̔ɉh�̓��ł���ƁB
�킪���h����t�͗܂��ׁA��������Ă��ꂽ�B
���̗܂��ꐶ�Y��Ȃ����A�����ɂȂ��Ă��A����Y��Ȃ����������������Ǝv���B
���{�l�͕��a�ł���A�K���Ȗ����A���ł���B���̂��Ƃ��܂��A�̂ɖ��������B
���Ɖ���
�q�ǂ�����̍ߖłڂ��ɁA�e�����X���s�֘A��Ă�������A�H����������e�F�s���ǂ�������N��ɂȂ����B
�����v���B���Ɖ����邩�B���Ɖ���ł��邩�B
�킩��Ȃ�����ǁA���̖�����B�u���x�͂����֍s�����A���x�͉���H�ׂ悤�v�����H�ׂ����A���������̖ʓ|�����Ă��ꂽ�e�̋�J���v���Η��s�₲�y���A�v���[���g�͂܂₩���ɉ߂��Ȃ����Ƃ������ł��킩����
���邪�A�ł����ꂵ���ł��Ȃ��A���ꂪ���߂Ă��́E�E�E�C�����B
���Ɖ���A���Ɖ��x�E�E�E�킩��Ȃ����A�P��ł������̊��ӂ̂��Ԃ����������B
��Ԗʔ�������
�l�Ԃ����Ă���̂���ԖO���Ȃ��B�w���`�A���X�g�����A�뉀�A���
�ǂ�ȏ�ʂɂ������ȊO�̐l�Ԃ������ς�����B
�����l�Ԃł������Ă���ƈӎ����Ă����ƌ����Ă��Ȃ��Ɩ��h���Ȋ�͂܂�ŕʐl�̂悤�ł���A�l�͑��ʓI�ł���A���ɉ��[���B
�{��ǂނ̂ɖO������A�d���ɔ�ꂽ��A�l�ԕs�M�ɂȂ肩������A�l�Ԋώ@������̂������B
����ȂƂ��ɁA�u���A�f�G�v�Ǝv���鉡���@��p�ɏo������肵�A�C�t���Ȃ������ɁA�V���Ȉ�����݂��邱�Ƃ�����B
�ڂ̍����A�����J�l�@�T���O���X�������Ȃ��C�^���A�l
NY�ł�������Ă�����{�l�F�B�Ɠ����ŏ��߂ĉ�����B
�Ȃ��s�v�c�ň�a�������X�B�ނ�͉Y�����Y�ɂȂ��Ă���悤�ŁA�����̂����Ȍ��ۂ��������肷��B�p���a��̓��{����E�E�E�B
�����ɂƂ��ē�����O�̂��Ƃł��A�ނ�ɂƂ��Ă͐V�N�ȗl�q�ł����Ȏ�������肷��B
�u�����H�ׂ����ł����H�v�ƕ�������A�uSASHIMI�v�Ƃ����Ă���Ƃ�����A�ǂ������{�l���ꂵ�Ă���B����A�V�V���[�ŏo������N�V�F�t�B�A�����ē����ōĉ�B�C�^���A�ŏo������ނ̓T���O���X�������āA�ꌩ�쐫�I�����e���ȕ��͋C���������o���Ă����B���{�Ō����ނ̓T���O���X�����Ă��炸�A�ƂĂ��D���������ɁB�u�Ȃ��ʐl�݂����ł��˂��v�u���{�ł͊F����T���O���X���ĂȂ��̂ŁA�����������ȂƎv���āE�E�E�v�B
�l�͏Z��ł��钬�⍑�ł��̕\�������ω�����B�Ⴄ�ꏊ�ŏo����Ă��C�t���Ȃ������B�l�͊��ɂ���ĕω�����B
�_�͉��̏ے��H
�F�B�̂���l���S���Ȃ����Ƃ��A�a�@�̗�����̓V��ɋ`����Ă��ĂƂ��Ă����������Ǝv�����Ƃ����b�������B
�����s���G�X�e�̕����̓V�����ɉ_��������ł���G���`����Ă���B
��D���ȃe���T�e���̂���Q��ɍs�����Ƃ��A���̕�n�̉��ɉ_���������B
���_�͊m���_�ɏ���ēo�ꂷ��H
�l�Ԃ��`���u�_�v�̃C���[�W���ƂĂ��s�v�c�ł���B
�Ȃ��Ȃ�ƕ����āA�}�ɐɂ����Ȃ�
�P�O�N�ȏ㈤�p���Ă���A����̏��X���R�����ŕX���邻�����B
���H���̒��ŏ��X�E����X�o�c�͑�ς��Ƃ悭�������A�X�̘b�� ��[�������b�Ȃ̂ɁA���������͕ʂƏ���Ɏv���Ă����̂ɁB
�Ȃ��Ȃ�ƕ����Ƌ}�Ɂu�ց[�A����Ȃ��B�v�Ǝv���Ɠ����Ɂu���݂����� ���v�Ƃ����C�����������Ă���B
���ɂƂ��ẮA�{���͑�D���ȓ����ꏊ�ł���A�C���]���_�ł���A ���C�n���ړ_�������̂ɁB
�l�̋C�������ق����ꏊ���A�����������Ă����B���݂����B
�������҂̗�
�v���Ԃ�Ɏ�҂̉������ς��B�m�荇���̑��q���o�Ă���A�ςɗ� �Ăق����Ƃ����Ă��ꂽ����B
�P�O��̖��҂̗��������ꐶ�����ɗx��A���A�̂��B
���ǂ��̎�҂́E�E�E�Ǝv���Ă����̂ɁA���̃X�e�[�W�ɗ����Ă��� �Q�O���̒j���͈Ⴄ�B�u���[�h�E�F�C���v���o�����B
�X�e�[�W�ɗ����Ƃ̉����͈�x�o������Y����Ȃ��͂��B
�������ڂŁA�͂�̂��鐺�ŁA�L�т��w�ŁE�E�E�B�������A�������B
���̗܂ɂ͂������܂��B�\���҂ɂ͐S����̐����肽���Ȃ�B
������Ă������҂ɂȂ��Ă��������I
�u���̐l�v
�u���Ȃ��͕��̐l�ł��ˁB�v�Ƃ悭������B�̐́A�V���N���[�h�����ǂ��Ă���Ă����W�v�V�[�ł����Ƃ��B
�X�̐l�Ƃ����̂́A�����Ƒ҂��đ����̂��̂���e�ł���l���Ƃ����B
���̐l�́A�����Ƃ��Ă��Ȃ��B�������Ƃ��Ȃ��A�܂�������B
�˂ɓ����Ă���B�����āA���M���������邻�����B�悭�l��������f�Șb��������Ȃ��B
�u���v�ɂ́A�䕗�Ƃ��k���Ƃ��J���Ƃ�������ۂ����邶��Ȃ����E�E�E�B
�ł��A�������Ă���B�m���Ɏ��͂������B
�����āA�Ȃ����W���f�B�I���O�̉̂��v���o�����E�E�E�B
�u����̖��h�v�͖��p�H
���X�A���݉��ŋC�������Ė��h�����Ƃ�����l������B
�������X������������A���n�������肷�邯��ǁA�����ŏo����đf�ʂ̐��E�ł��������������̌㑱�����E�E�E�Ƃ����̂͐����Ȃ��B
�����Ă������������h�̐�ɘA��������̂́A�ǂ����p���������悤�ȁE�E�B
����ł͖��h�͂Ȃ��Ă����������B
����������ł���Ƃ��y�����Ă��A���ɂȂ�Ƃ��炫���܂�Ȃ��l�����邵�E�E�B����͎���̂��������B�|���ł��U���ł��Ȃ�ł��n�j�B�ƍŋ߁A����̂�������������Ƃ��������ł���悤�ɂȂ��������B�@
�ł��邱�Ƃł�������A������邱��
�_�˂�V���̐k�Ђ̂Ƃ��A�Z�����ă{�����e�B�A�ɂ����Ȃ��������Ƃ�������Ƃ�������A�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�ł���Ƃ��ɁA�������Ǝv�����Ƃ��ɂ���悢�̂�����B�������Ă��ł��Ȃ��Ƃ��A���Ɏ����ɂƂ��ėD�揇�ʂ��������Ƃ�����̂ł���A����͎d���Ȃ��B�{�����e�B�A�Ƃ͉��̋삯�����Ƃ������ɁA�܂��Ɏ��玩���I�ɍs���ł��邱�Ƃ��w���B����͐l�̂��߂ł͂Ȃ������̂��߂ł���B�܂��傫�Ȃ��Ƃ����邱�Ƃ������悢�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�������ł��邱�ƁA�����Ȃ��Ƃł悢����A���悤�Ǝv�����Ƃ��A�ł���Ǝv�����Ƃ��ɂ����s�����邱�Ƃ���B�������ʼn������Ȃ��l���A�ق��Ă������ƍs������l���������B����Ȃ��Ƃ������Ȑl���狳����ꂽ�Q�O�O�S�N���B
�S�ɉi���Ɏc�鑡�蕨
�a�����₢���ȋL�O���ɑ���A�܂����������v���[���g�B��������悢���l����̂��y�����B��p�o���ɍs�����ۂɁA�F�l�����ꂽ�v��ʒa�����v���[���g�B
����͔����傫�ȉԑ��������B�u�Ԃ͓��{�Ɏ����ċA�邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ǁA��p�ɂ���2���ԁA�y���߂܂�����v�B���̌��t�͍ō��������B�m���ɉԂ͂ǂ�ȃM�t�g�V�[���ɂ����\�I��B�͂��܂ł̌���ꂽ���Ԃ�ɂ��݂Ȃ���߂����̂��悢�B�܂��Ƀ��m�ł͂Ȃ��A�S�邱�Ƃ̑�����w�B
�
�ϋq�́u���ڂ���v�ł͂Ȃ�
�吨�̑O�Řb������A�̂����肷��Ƃ��A�悭�u���ڂ���Ǝv���Ȃ����v�Ƃ���ꂽ�B�Ƃ��낪�ǂ������A�ϋq�͂��ڂ���ǂ���ł͂Ȃ��B�ދ���������A�Q�Ă��܂���������Ȃ��B�O�����瑼�����l���n�߂邩������Ȃ��B���ɂƂ��āA�ϋq�͂Ƃ��Ă��|���u���v�ł���B�u�ԏu�Ԃ��Ȃ�������ɂ��Ȃ��A�ō��̂����ĂȂ��A�ō��̃l�^���X�e�[�W�ɗ��l�͐S�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�
�l�������͌����T�C�g�ŁH
���Z����̓������������Ȃ�web�̌f���ɏ�������ł����B�Q�R�N�Ԃ�̍ĉ�H�ƂȂ����B�Ȃ�ł��A�����T�C�g�Ŗ��O����ꂽ��z�[���y�[�W���o�Ă����Ƃ̂��ƁB�����l�b�g���Ȃ�������ꐶ����Ƃ��Ȃ�������������Ȃ����F�B����ȕ����̗͂ōĉ�ł����F����A�����������ނ��ł��������Ǝv���B����ɂ��Ă��A�l�̖��O����������Ƃ����̂́A�܂��ɂ킭�킭�uwanted�v�ȋC���B������l��������A�܂��͖��O�����Ă݂�H
�
�l���̃o�����X���Ƃ邽�߂�
�`�����e�B�I�[�N�V�����ŏW�܂����������s���N���{���^��������Ă���c�̂֊�t�ɍs�����B���d�������Ȃ���A���K�����������̊���������{�����e�B�A�c�̂��^�c����Ă���J-POSH�̏��c���܁B�u�d�������̐l���ł͂Ȃ��A�o�����X�̂Ƃꂽ�l���ɂ��邽�߂ɂ���Ȋ��������Ă����ł���v�Ƃ������t�ɃW�[���B
�����A�{�����e�B�A�ł������A��ł����ׂĂ̊����́A���������ړI�ł���Ƃ����B
�����������v�����Ƃ��ǂ�ǂ�s���Ɉڂ��Ă������Ǝv���B����͂���ς莩�����g�̃o�����X�̂��߂Ȃ̂ł���B
�
�u�����@����߂Ⴑ�v
��D���Ȃ��D�ݏĂ��B�f�G�Ȃ��X�𐢊E�I�ɓW�J���Ă��邠�̐�[�̒���В��̍u�������B�ǂ����Ƃ��Ă������I�Ȃ��b�ŁA�S�g�܂邲�Ƌ��������A���̂Ȃ��ł��A��Ԉ�ۂɎc�����̂́A�������C�s����́u����߂Ⴑ�v�Ƃ̑Θb�B�ڕ���}�邽�߁A����ɓ����ꂽ����߂Ⴑ�B�ӂƁA����̗��ɂւ���Ă��邿��߂Ⴑ�����āA�u�����B�����P��`�����X��邩��A���x�͂���ɓ����v�Ɛ���������ꂽ�Ƃ��B�������ڂ�̉\�����������猩�o�����Ƃ�����ꂽ�B
�l�Ԃ́A�����݂ȁA����߂Ⴑ�Ɠ����B�ǂ�Ȃ���ɂ�����ꂽ���̂��E�E�E�E���l���ǂ���B���̔��z�E���_�������ꂽ�A���̕��ɂ͂��ЂƂ��܂�����������B
�l�Ԃ́A�ǂ�ȏ�ʂł����̋C�ɂȂ�A�w�Ԃ��Ƃ��ł���B�f���炵���I
�
�}�[�P�b�^�[�ɂ́u�F�C�v���s��
�悭�u���ȂŃ}�[�P�e�B���O�Ƃ́E�E�E�Ƃ����b�����邪�A�ŋߎv���̂́A������h������̂́A�l�X�́u�F�C�v���Ǝv���B��肫�ꂢ�Ɍ��������A�������悭��������
���̐l�ƈꏏ�Ɋy���݂����E�E�ꏏ�ɔ����������̂�H�ׂ����E�E�E����ȗ~���Ɍ������������̂��r�W�l�X�Ƃ��Đ������Ă���Ⴊ�����B�܂����̗~���ɑ��鉿�i�́A������悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�����Ă������x��������ΐl�͍��z���J���B
���{�̃}�[�P�e�B���O���ґ�Ȏ���ɓ˓����Ă���Ƃ����邪�A�F�C�Ƃ͐l�Ԃ��������ŕs���ȃG�������c�ł��邱�Ƃ��Y��Ȃ��ł������B
�����ɂȂ��Ă��A�F�C���Ȃ����Ă͂����܂���ˁB
�S�̋����_��
�@�l�͂Ȃ��u�����_���v��ڎw���̂��B����͏����̈���A���̏ے�������A���ɂ́u�ꓙ�܁v������E�E�E�E�B�����Ă���́A�����Ƃ̓����ɏ������u���v�ł����邱�ƂɈ�Ԃ̉��l������B
���͑������邱�Ƃ��A������Ԃ��Ƃ��A�������������Ƃ��ł��Ȃ��B�ł��A���Ȃ�̃��_�������߂Ė����𑖂��Ă���B���̃��_���́u�����Ȋ����v�Ƃ����ڂɌ����Ȃ����_���ł���B�����Ă���ԂɁA�����̃��_�����W�߂��邾�낤�B����Ȃ��Ƃ��ӎ����邾���ŁA�������S�n�悢�ْ��ɕ�܂��B
�I�����s�b�N�͐l���̏k�}���B
NY�֍s�������a
�Q�T�ł͂��߂Ă̊C�O�E�E���ꂪNY�������B�P�T�N�ԁA�������x��������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B���ꂮ�炢���̒��Ƀn�}���Ă��܂����B
�t�@�b�V�����A�t�[�h�A�A�[�g�A�l�ԁE�E�����̋����S�����ׂĂ��̒��ɂ���B
�����������_��b���邽�߁A�j���[�G�i�W�[��u�ō��̊�n�v�ł���B
�����炢�ł��s�������Ƃ��ɑ����^��ł����E�E�B
�R�����Ɉ�x�A�P���ł������炠�̋�C�ɐG�ꂽ���I�Ƃ�����]������Ԃ�
�����̊��͂͐����Ȃ��ƐM���Ă���B
�S�����������ɂ́A�ӂƖڂ����B���b�N�t�F���[�̋���N���X�}�X�c���[���A�Z���g�����p�[�N�ɐς������v���o���B�����ɂ͎��̃\�E���V�[����
����B�����āA�܂������Ɍ��������߂̃G�l���M�[���N���Ă���B
�Ƒ��̒a����
���̊Ԃɂ��A�Ƒ��̒a�������Ɏv���悤�ɂȂ����B
���e�̒a�����ɂ́u���Ȃ������Ă��ꂽ�������ŁE�E�E�v�Ɗ��ӂ̋C����
��`�������B�l���̌㔼����ނ�̒a�����A�܂������ƂS�O����j�����Ƃ͂ł��Ȃ�����A���߂ĂP��1���Y�ꂸ�ɂ������B
65�ɂȂ�����e�͎d�������Ă���B�u�����N��ŁA����ǂ���v���̌��t��
�u�����A�����v�Ɩ��ӔC�ȉ����B�ł��A�ł�������ƌ����ł��Ăق����Ƃ����肢������A�����Ĕޏ����������N�܂ŁA�����������˂Ȃ�Ȃ��I�Ǝ����g���ە����Ă���B
�a�����Ƃ����̂́A���ւ̊��ӂ��Ċm�F�ł���A�ō��̋L�O���ł���B
�����]
��p�֍s���ƁA�u���̐l�͕���ŁE�E�E�v�Ƃ����b���B���~�ł���Ȃ���
�l�̂��߂ɖ��ɗ��Ƃ��Ƃ��Ă���l�A���̐l���g���牽���n�b�s�[�z�������H���o�Ă���l�����Ԃɂ͏��Ȃ��炸����B
���������l�ɂ͒m��ʂ����ɐl���W�܂邻�����B
���������́A���e���`���Ă��Ȃ�����Ȃ��B
���ʂ��A�l�ɗD��������A���ɗ����Ƃ��ő�̌c�тƂ��ē��X����B
���̐ςݏd�˂��u����v�ɂȂ�錍���낤���B��V���̂��̂��낤���H
������ɂ��Ă��A�Ί���₳���A���������炷�E�E�E����ȁu�C������v�l�ɂȂ肽���B
�ËL��Y��܂���
���w���̍��A�ËL�͋�肾�����B�W������Ίo�����邪�A�{���ɗ������Ă��Ȃ����Ƃ��C���v�b�g���邱�Ƃ͈Ӗ����Ȃ��Ǝv������E�E�B
�������̐�����A��͂�푈�ňËL�����A���Ђ��ł����āA���̐킢��˔j���A�Љ�l�ɂȂ��Ă����l�������B�u�G���[�g�v�̒�`�͂킩��Ȃ����A
���t�����m���Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��Ƃ������Ƃ�������Ɋ�����B
��Ȃ��Ƃ́A�������̌��A�����E�E�E�B
���ꂪ�d���ɖ𗧂�����A�L���Ȑl�ԊW�ɒʂ����肷��E�E�E�B
�S�O��̕��Ƃ͉����B�����ƌo�����b�q�ɓ����P�����Ǝv���B
�����炱���Ⴂ�Ƃ�����̑̌���������B���ł��x���Ȃ��B�����ƒ��ɏo�āA
�l�ɏo����E�E�B
�������͒���������H
�Q�O��̍��A�I���i�͋�������������A���������B�Ƃ���ꂽ���Ƃ�����B
�܂��o���s�ׂ́A�̓��ɂ����Ԃ鈫��������O�֏o���A���邱�Ƃ�����A
���������Ƃ͊m���ɃX�b�L������B�B������S�V���ɃX�^�[�g�ł���Ƃ������Ƃ炵���B�j�͊i�D�������狃���Ȃ��B������S�̓ł��̓��ɒ~�ς���A���ꂪ�a�C�̌����ɂ��Ȃ葁���ɂ���E�E�E�Ƃ��B�^�U�͒肩�łȂ����A�܂𗬂����Ƃ͊m���ɋC�����������Ƃ�������Ȃ��B��{���y�B�ǂ̏�ʂɂ��܂͓o�ꂷ��B
�悭���A�Ƃ��ɂ͋����A�{��E�E�悭������B�܂��o�Ȃ��l���͕��R���B
�Ƃ���ōŌ�ɋ������̂͂��ł����H
��M�V���R���@�G�i�W�[�V���R��
�ȑO�p���̒n���S�ŃX���ɑ������Ƃ��A�����Ă��ꂽ�p���W�����k�����y�����Ă��ꂽ �}�b�N�̃u���E�j�[�B�u�V���R���͌��C�ɂȂ�H�ו���A�����A�H�ׂȂ����v�ƁB
����ȗ��A����ŃV���R�����݂���̂��y���݂̂ЂƂB�ŋ߂��C�ɓ���x�l�`�A��`�ł݂����y�y�����`�[�m����`���R�ƁE�E�E�B�����o�b�O�ɂق�̈ꗱ�E���Ă����������@�̖�ł���B
�������Ă��邾���ŁA�������邾���ł́u�K���v��ԁB
�m�x�̃^�C���Y�X�N�G�A�̃z�e���R�V�K�̊p�����B��������́A�n�h�\�����o�[�Ƃm�x�̍��w�r���Q����]�ł���B�����Đ��ꂽ���̗[���͍ō��B�Â��ɐÂ��ɍ����Ƃ������������̂Ȃ�1���̃J�[�e���R�[���������̂��D�����B�����ɏZ�݂Ȃ�����A�Ƃ��ǂ����̕��i�ɐg�����������Ȃ�B���X�����̋��ꏊ��ς��邱�ƂŁA�V�N�Ȕ��z���N�����肷��B�ł���A1�ӏ��ł͂Ȃ����ӏ��������̋��ꏊ�������Ă������B
�������Ă��邾���ŋ��邾���ŁE�E�S���a�݁A�͂��N���@�����MY FAVORITE CITY �E�E�m�x�ł���B
�݂�Ȑl���Ƃ����u�X�e�[�W�v���Ă���
�ǂ�Ȑl���A���ꂼ��̐l���������Ă���Ȃ��Ǝ��X�v���B�����Ȋ�E�����������āE�E�E�B�����������钆�Ŏ������g��͍��������Ă���E�E�E�B
�����̐l�����X�e�[�W�Ǝv�����ǂ����͐l����B���͂����v���悤�ɂȂ��Ă���A���ւ̎����E������肪�����Ȃ����悤�Ɏv���B
�m�x�֍s���ƕK������ɑ����^�сA�~���[�W�J�����ς�B���̃X�e�[�W�ɏオ���̂͌������P�����d�ˁA�����ċ��^�����������҂����ł���B�ނ�̉��Z���ς邽�тɁA�����̐������͂܂��܂��Ǝv���B�X�e�[�W�ɗ��l�́A���s��������Ȃ��B�u�ԂɊϋq��ۂݍ��݁A������^����B���t�ŕ\���ł��Ȃ��p���[����o����B���ْ̋��������܂�Ȃ��D���ł���B
�����̒�����ォ�猩��@�@
�ǂƂ͉����B�����ɂ���āA�܂������Ⴄ�ʂ������Ă��܂����Ƃ�����B
�ǂ�ǂƊ����Ȃ����߂ɂ́A�ォ����ՂŃ��m������K���Â��肪�K�v�ł���B
�ǂ����Ȃ���������ڎw�����Ƃ����Ӗ��B
HISTORY�́u�ނ̕���v
�ǂ�Ȑl�ɂ��A�ǂ�ȏ��i�ɂ�HISTORY������B�w�i�͂ƂĂ���B���̐l��m�̑�ȃG�������c�ł��邾���łȂ��A���̑��݂��̂��̂ł��邩��B
����l�Ƙb�����Ă���Ƃ��uHISTORY�v�Ƃ́uHIS�@STORY�v�ł��邱�Ƃ�m�����B�ނƂ́uGOD�v�B���j�Ƃ͐_���n�������ꂾ�������B
���ׂĂ̌��ۂ͋��R�ł͂Ȃ��K�R���Ƃ������Ƃ��B���̃��m�̌����͂܂��Ɏ�������������Ă��鑶�݂ł��邱�Ƃ�m��ƂƂ��ɁA�ǂ�Ȃ��̂ɂ��uHISTORY�v�����邱�Ƃ̈Ӗ����l����������B
���āAMY STORY�́c�A�~�X�e���[�H�B
�����̟N�A���̂�����
���{�şN����Ԏ������̂́A���s���Ǝv���B�����̟N�͂ǂ����j���I�ȍ炫�������A���s�̂�����́A�͂�Ȃ�A�₳�����A�͂��Ȃ��c����̏����̃C���[�W�B
���āA�l����N�ɂ��Ƃ���B�������炭�̂͏u�Ԃ�������Ȃ��B�����č炢����U���Ă��܂��Ƃ���������������B�ł��A�N�ɂł��J�Ԃ̋G�߂�����͂����B���̂Ƃ����y���݂ɏu�ԏu�Ԃ�ɂ��݂Ȃ��琶���Ă݂���ǂ����낤���B
�^�N�V�[�h���C�o�[�^��
�^�N�V�[�ɏ���āA�h���C�o�[�Ƙb���̂��ʔ����B�����Ȑl�������̓s�x�����ł���B�����ȓ��@�������āA���̓��ɐi��ł�����B�b���Ċy�����A������������v���̃^�N�V�[�h���C�o�[���Ǝv���Ă���B���������S�^�]�͑�O��B
����̂��ꂵ���b�A���s�̃z�e������w�܂ŏ�����Ԃ̃h���C�o�[���u�����͉J�ŁA�Ԃ��a���Ă��܂��܂������A���Ȃ��̂悤�Ȃ��q����ɏo����ĂƂ��Ă��y���������ł���v�Ƃ����Ă���A�Ԃ��~�肽��A���܂ł����U���Ă��ꂽ�B
�V���͖���Ƃ���H
�V�����Ăǂ�ȂƂ���H�l�������Ƃ��Ȃ����A���[���b�p�̋���Ō���@����ł͓V�g�̃C���[�W�H�Ƃ���z�e���ŁuHEAVENLY BED�v�Ƃ����ӂ�ӂ�ŐS�n�悢�Q����J���A�q���Ŏg���̂͂������A�ʔ̂��͂��߂��B�܂�œV���ɂ��邩�̂悤�ȐQ�S�n���B
��ԁA�l���K����������̂͂�����������A�u�O�b�h�X���[�s���O�v�Ȃ̂�������Ȃ��B���̃x�b�h�����߁A���͗��ɏo��̂��D�����B
��Ԃ̂��y��
���X�A�ō����₢���ȏW�܂�ŊO�H�������B�b��̓X��V�����X�����X�͍s���B�O���ɍs���z�e���Ń��[���T�[�r�X���Ƃ�B�H�ׂ邱�Ƃɂ͑I�������������鍡�����̍��B
�ł��A���X�u�����A�������Ă̔����͂�ɐ����܂��Əݖ��������ĐH�ׂ����v�Ǝv���A���ꂪ��������Ɩ{���ɖ������ꂽ�C�����ɂȂ�B�q�ǂ��̂Ƃ��ɂ��y���Ǝv�����H���̂���l�ɂȂ��Ă����̂܂܂̂悤���B���ꂪ�\�E���t�[�h�Ƃ������̂��낤�B����Ȃ��Ƃ��v�����炢�A���̐H�����͖L���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��낤���B����ł���B
