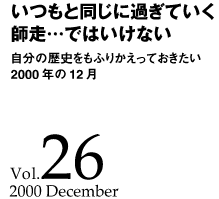|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
「ミレニアム」ももうすぐ使えない…
「ミレニアム」という言葉が日本で流行りだしたのは確か1999年の後半だった。2000年にはあれしましょう。これしましょうと旅行会社、ホテル、飲料メーカーなどなどどこもここもが、ミレニアム商法に便乗した。
2010年まで保存できるというタイムカプセルのようなカップラーメンを開発した会社もあった。この2000年のおかげでビジネスがうまくいった人も少なくないだろう。(そういえば、2000年問題と騒いでいた時から1年が経つのか??)そして、その商法も1000年後まで使えなくなる、カウントダウンである。
ビジネスとして、生活者として、人としてのクリスマス
今、ニューヨークに来ている。まさにクリスマス前、街はどこもここも、活気に満ち溢れている。日本のクリスマス商戦とは、年末年始を迎えるにあたっての今年最後の「ハレ」の場的な意味合いが強いが、キリスト教国である当地でのクリスマスは、もっと本格的である。
街中の店のクリスマスディスプレイはどこも目をみはるほど輝いており、ココロが入っている。ショーウィンドはどれも撮影しておきたい小粋な作品ばかりである。また歩いているだけでクリスマスキャロルが必ず耳に入ってくる。思わず鼻歌が出てしまう。毎日のように、クリスマスコンサートが開催され、深夜からパーティーに出かける人も少なくない。
このシーズンは、ギフトマーケットも通年で最大規模となる。人々は、家族や恋人への贈り物、また自分へのご褒美、パーティーへのおしゃれ着とアクセサリー。一年間でもっとも財布の紐がゆるむのは、日本もNYも同じようである。
ひとつ、面白いことがあった。商品をどんどん薦める店員がいて、「こんなにたくさん買うの?」と聞くと、「いいじゃない、ハッピークリスマスだもの」と応えた。そういわれると買うしかなくなる。これぞ、プロのセールスと納得した。
さて、そんな楽しいクリスマスばかりではない。教会へ行く。中世から歌い継がれているクリスマスキャロルにじっくり耳を傾ける。キリストの誕生を信じ、それを祝う人々にとっては、クリスマスとは単なるギフト交換、楽しいお祭りのひとときというだけではない。これは、自分の生命の根本をも見つめなおす大切な、荘厳な時間でもあるのだ。自分の存在を改めて確認し、周りに、神に感謝する。お互いの尊厳を認め、新たなスタートを祝う。と、そういうことなのだろう。
キリスト教徒でもないくせに…ハッピークリスマス
もともとクリスチャンでもない者が、2000年だとか21世紀で騒ぐ意味はない。でも、やはりなぜかこの西暦の中で、生を受け、その時間の流れの中で生きていたわけで、その区切りは意識せざるを得ない。逆にいえば、キリスト教文化の力は絶大だと認めざるを得ない。ほとんどの日本人が、毎年年末には大掃除をして、新年には年賀状を書き、すべてを新しくして1年を始める。誰にとっても、生活の定期的な区切りは必要である。
もし、区切りがなければ、見直す行為自体が難しく、気持ちを入れ替えることもできない。そういう意味ではこの2000年は、宗教に関係なく、皆それぞれが自身を見つめなおし、新たにスタートするには、最高の節目であると思う。
人は30歳とか40歳とかキリのいいところで見直す一般的な慣例があるようだ。(もうすぐ不惑?いや惑う)
今回は、20世紀の中で生きてきた自分を見つめなおしてみてはどうだろうか。自分が何歳であれ、歴史の大きな通過点に生存していることは、大きな事件である。感動もする。たとえば、生まれたとき世の中はどうであったのか。それから、今日まで環境はどのように変わり、自分はどのように生きてきたのか。なかなか自分の誕生日の振り返りには見えないことが、この「節目」には見えてくることもあるだろう。新たなる発見である。
私は、改めてこの2000年のカーテンコールを前に、自分がこの大きな節目に生きていられることは、とてもラッキーであると感じている。平和ないい時代に生まれた。20世紀の最大の事件は世界大戦であろうが、それも体験することなく、プラスの戦渦の中で育ってきたと思う。豊かなモノに囲まれて、元気な日本に守られて…。しかし、21世紀の到来を目前に、いろんなことが変わろうとしていることを最近感じる。環境の変化を意識するが故に、自分のありようが見えてくる。そんな気がする。
いつもどおりの年末でいい。でも、少しだけ意識していたい。改めて感謝することと、20世紀が与えてくれたいい文化、哲学を生かしながら、21世紀を生きることを。ちょっと大げさになってしまった。
原稿を書いている窓の外は、雪のセントラルパークである。ここで20世紀最後のプチ通信を書いていられることもまた有難い。
さあ、買い込んだシャンパンやワインで楽しく乾杯!
皆様、20世紀大変お世話になりました。2001年からも、元気に、やさしく進みたいと思います。
よろしくご指導いただきますよう、お願い申し上げます。