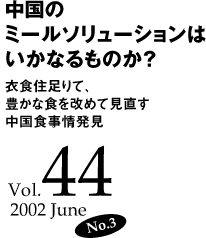|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
中国はとてつもなく大きな国である。上海だけでも1600万人いるという。
以前、中国人の友人に「どうして中国の食事はおいしいの?」とたずねたら「食べることが一番大切だから」と答え、また仕事をするにも食に関する仕事をするのが、てっとり早く確実であるということも教えてくれた。確かに多くの命を支えるには、他をおいても「食事」だろう。
2008年のオリンピック、2010年の上海万博(まだ最終決定ではないという話も聞くが、見ているとあたかも決定したかのような盛り上がりようだ)を目前に、中国はますます変化を見せている。上海浦東空港から上海市内まで現在タクシーで1時間余りであるが、じきに8分で移動できるリニアモーターカーが登場するらしい。おっそろしい! 決まったらすぐ作ってしまうのだ。この国は! 世界中がこの中国に注目をし、生産拠点ではなく、可能性ある市場として参入に必死である。もちろん日系企業も然りである。
上海をはじめとした大都市の人々の所得は年々上昇し、マンションを20代で購入したりする、ニューリッチ層も増えている。10年前、はじめて香港から広州へ入り、なんと多くの工場ができているのかと驚いたあの頃から比べると、今は、毎月訪れるたびごとに新しく、しかもセンスのよいビルやショッピングモールなどが増えていること、そして、なんといっても中国の女性たちが美しくなってきたことに驚きを感じる。10年前、中国人は笑わないと思っていた。だから、サービス業なんてありえないと思っていたが、今は違う。と、このようなめまぐるしい変化を続け、我々にとって脅威でもある中国……。
都市部では一見、衣食住とも事足り、大変豊かになってきている。そして、今後ますます成長していくことが予想できるが、その現状のなかで、本家本元「食」の領域はどうなっていくのであろうか?いくつかの現場を訪問してみた。
その1 日系企業が中国に進出している。これまで生産の拠点であったが、これからは市場としての中国である。しかし、日本製の商品がそのまま中国に受け入れられるとは限らない。そういう意味では、マーケティングリサーチというビジネスが拡大しつつある。正確な人口もわからないような、アバウトな巨大龍、中国においても、定性、定量調査がよく行われている。街角調査からネットを使ったリサーチまで。これらの結果をもとに、商品の現地化を推し進める例も多い。
ちなみに、グリコのポッキーは大人気商品であるが、日本で売っていないフレイバーが販売されていたりする。日清のカップラーメンも日本より品種が豊富である。
その2 外食が多い中国マーケットといっても、多くの家庭では内食である。男女を問わず仕事を早く終えた者、あるいは地方から出てきたお手伝いさん(上海では住み込みお手伝いさんの給料が安い)が毎日の食事を作る。そのときに使われる調味料。たとえば醤油という日本で欠かせない調味料、今これが中国市場に出始めている。キッコーマンでは、上海周辺の昆山という町に工場をオープンさせた。中国にはもともと伝統的な醤油があり、中華料理には欠かせない調味料であった。一方、日本のそれとは、香りもコクも異なり、醸造させた分だけ値段も高い。しかし、この高級な日本の醤油は和食にもっとも合うものとして、今後の中国の食生活の高級化に伴って普及するであろうという試みである。
確かに、今、和食が上海でも人気である。高級日本醤油が伝統的な中国の醤油と使い分けされ、各家庭に入り込むにはそれほど時間を要さないであろう。面白い話を思い出した。上海の大手スーパーで、日本の醤油に試食会を行う際に用いられる食材は「鶉のたまご」らしい。これだと、醤油のおいしさがよくわかるそうだ。本当は刺身とかが合うと思うのであるが……。コストが合うわけないからか? なんとも中国らしい試食だ。
その3 今、上海の外食産業での和食の主流は、「食べ放題、飲み放題」である。日本でも80年代に、食べ放題が流行ったが、これはバイキングであった。上海のそれは、そうではない。いわゆる普通の居酒屋・割烹スタイルで、定価メニューがあり、そこから好きな料理を、酒を好きなだけ注文していいというやり方である。また、時間制限もない。刺身、てんぷら、寿司、なべ料理から、漬物もろきゅー……にいたるまで、日本の和食レストランで出てくるようなメニューがそのまま体験でき、しかも心ゆくまで食することができる。そして気になる値段は150~200元。日本円で2000円から3000円。これは大変お値打ちであると、今、上海の人々に大人気で、このような食べ放題の店が増えておりまた、ホテル内の和食レストランでも週末は食べ放題企画を行っているところもある。
中国における和食はこのように、広がりつつある。食べ放題の店で、まずは気になるメニューをオーダーし、気に入れば、和食をもっと好んで食べることになる。そのうち、食べ放題ではないお店で、寿司や刺身、てんぷらを注文するようになる。食べ放題はトライアルには効果的な方法である。一見、高価であるとされている和食が、リーズナブルなカタチで上海市場に浸透していることは興味深い。現在、上海市場で250店あるといわれている和食屋。今後のゆくえはいかがなものか?
その4 中国でも食に対する安全・安心の意識が高まりつつある。たとえば、台湾人経営のオーガニックレストランが近所の住民に大変受けている。豆腐やきのこ類をたくみに利用した、精進料理=素食(中国ではそう呼ぶ)が健康志向の人々には大人気である。日本人駐在員妻たちにも受けがよい。一方、野菜などの自然食材について、年々法が整備され、現在では、有機食品、緑色食品、無公害食品、普通食品との区別がなされ、一般の市場に出回っている。オーガニック食品を認知している人はまだわずかであるらしいが、すでに高級スーパー(カルフール含む)では、有機野菜を販売するコーナーもあり、一定の支持を集めている。また、食品メーカーでも日本を市場に考えている企業では、いち早く有機食品の認定を取得し、安心安全な食品を日本へ供給するといった例も現れている。
某フライドチキンの会社が一度、チキンを揚げた油を街角の屋台に提供していたことが分かり、社会の不安と不審を買った。ダイエットビジネスなども流行し、ダイエット・健康志向が高まりつつあるなか、そういった如何にもといった事件が巷では起きており、人々はある程度の覚悟を決めつつ、街角のマーケットで買い物をし、屋台で点心を買ったりしているのだ。しかし、コンビ二やスーパーの台頭により、安心して食材を買い求めることが当たり前になっていけば、街角の市場や屋台は廃れていくと予想できる。
その5 上海著名ホテルチェーンの系列にパン屋がある。上海市内に約20店舗ほどある。昔は伝統的な中国パンを焼いて売っていた店が多かったが、欧米パンを焼き、販売する店が登場すると、多少高くても、香りも味もよいとされ、圧倒的にそちらが支持されるようになり、伝統パンはなくなった。今、そのパン屋では、フランスパンフェアを実施しており、食事パンのほか、菓子パン、ケーキ(おやつ用と記念日用)を販売している。おどろいたのは、そのパン屋には、おじいさんやおばあさんが買いにくるというという風景。彼らにとっても、焼きたてパンはおいしい日常食と化している。飲茶ばかりが中国人の食事ではなくなってきているのだ。
また中国人は、集まりごとやパーティーが好きなようだ。記念日には思い思いのオリジナルケーキを注文し、店頭へとりに来る。店では豪華なデコレーションケーキの実演も行っている。ピンク、紫、オレンジ、たっぷりクリーム……。いかにも人工着色料をふんだんに使ったケーキではあるが、大変美しく、飾っておきたくなる代物である。1個2000円程度で、よく売れるらしい。
こんな風に、上海では和食だけでなく、欧米食もどんどん日常化しているのだ。
その6 上海には台湾人が30万人いるらしい。しかも中国における彼らの位置づけはとてもリッチという点。いろんな新しいビジネスを興し、成功している。飲食においても同様である。昨年できた観光スポット「新天地」では、ネオシノアともいうべき、新しい中国のライフスタイルの提案が見られる、建築、ファッション、食において、新しい息吹を感じる快適空間である。そこにも台湾人が多く進出、出店している。
高級なガラス文化を飲食に応用させたレストラン、アマンリゾートのデザイナーが手がけたというおしゃれなイタリアンレストラン、そして活躍するデザイナーと手を組む、現代的な本格中華レストラン。これらの動きを見ていると、食が単に食べるという行為から、空間・時間を楽しむ娯楽に変化していることに気づく。また、伝統と斬新、あるいは東洋と西洋、あるいは食と空間……と、食は異文化と融合し、新たな文化へと変貌を遂げていることを感じ取る。
上海の食はやはり奥が深いと痛感する。
1元から1000元まで、価格も多様であり種類も豊富である。でも、1元で十分におなかも満足でき、おいしくいただける物があるという前提で楽しみ方を考えたいと思う。食は高いほど価値があるというものでは、決してない。楽しいか、おいしいか。である。中国のミールソリューションの次のステップにますます注目していきたい。