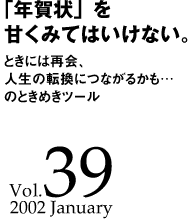|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
年賀状。これは日本の象徴的な文化ではないだろうか。欧米ではもちろんクリスマスカードが習慣化されてはいるが、ビジネスでなく、プライベートの世界で国民一人100枚単位で、それぞれが趣向をこらして作成し、元旦に届くように一斉に送る…という習慣はどこの国にもないはずである。郵便屋さんにとっては1年でもっとも多忙な時期。最近はコンビニや文具屋でも印刷の受けつけに忙しい。外国のコンビニや文具屋にはこのサービスはない。
今日までこの年賀状の習慣が残っているのは、お年玉をハガキにつけたという天才的な販促アイデアと、郵政の方々の弛まない啓蒙活動の賜物であり、そして日本人特有の律儀さ、真面目さのおかげであろう。
パソコンの普及により、年賀も電子メールにとって変わるであろうと予想されていたにも関わらず、近年、パソコンの利用者拡大によって、自己流の、オリジナリティの高い年賀状づくりを楽しむ人も増え、日本の文化としての年賀状はますます健在といえる。
子供の頃の年賀状。どんな思い出があるだろうか?正直、あまり心当たりがない。なぜならば子供時代の交遊関係は学校の友達がほとんどで、冬休み前まで一緒にすごしていた仲間からハガキが送られてきても、それほど感激はない。しかも確かに、子供時代は年賀状を印刷させてもらえるほど、豊かではなかったし、7日になったら学校で友達に会えるのだから出す必要はないといわれた。自分で作った年賀状の思い出は、例の「みかん汁のあぶり出し」ぐらいか?
思えば、30代前半まで、それほど年賀状についてあれこれと考えたことはなかったように思う。これまでは少し儀礼的な、事務的な感じというか、新年だけじゃなくて普段からきちんとコミュニケーションすればよいのだから……とかどうして会社の人に一々出す必要があるのだろう、面倒くさい。何もアラタマル必要はないとかなんとか突っ張っていたようにも思う。
それでも、岐阜の田舎を離れ、京都、東京と住まいを変わるうちに、年賀状でしか会えない人も多くなり、年賀状のやりとりが途絶えるともう行方不明状態……になってしまう場合もあり、そういう意味では毎年自分を思い出し、筆をとっていただける人を有難く思ったものだし、今もその気持ちは変わらない。
「今年こそ会いましょう」を合言葉にもう十年、二十年も再会を果たしていない人は多いのではないか。1年という月日はとてもあっけなく、年末年始に再会を決意してそんな思いをやりとりしても、実際に再会できるのは何十分の一ではないか。普段の生活の中で、何十年も会っていない旧友や恩師に会うという場面は正直難しい。田舎に帰ったり、何かきっかけがないと、またなかなか気合を入れないと実現しないものなのだ。とそんなことを思うけれども、新年に届くハガキを見て、今年こそはと思い、そして年末にハガキを整理、処分するときに「今年も会えなかった、来年こそ」と思って、その気持ちを年賀状に託すわけだ。
3年前から、年賀状には自分のメッセージを表現することにしている。
毎年のテーマを決め、それを表明し、そのテーマに沿って1年間を生きようと、一応は決めている。はじめは「おかげさまでぴょん、ぴょん、ぴょん」(独立した年)そのあとは「Performing
small objectives results valuable fruit.」、「21世紀へのsouvenir」と続き、今年は「『いのち』を感じながら『この瞬間』を大切に」だ。
その前年を振り返り、新年に向けての清い?気持ちと強い意志をこめているつもりだ。昨年は例のテロに間接的に巻き込まれたことがこのテーマとなった。そして、年賀状を見て、すぐに反応してくださる方もある。
「命拾いしてよかったね」「素敵なメッセージをありがとう」「ホームページ見たよ」「ピアノの演奏はどこ?いつ?」「○○日に東京へ行くから会おうよ」……。有難いことである。何年も、十何年も止まっていたおつきあいの時計が再び動き出す……ということもあるのだ。
年賀状は決まりごとではない。義務ですべきことでもない。私の場合は、大切なコミュニケーションツールのひとつとして考えている。
あるがままの自分をお伝えしたい。だからできる限り、手作りのぬくもりを残したいと。パソコンのおかげで、文字を書く時間が減ってしまった。だから年賀状は手書きもいいのではないか?そして、必ずひとりひとりへ違ったメッセージを書き添えるようにしている。
年賀状はまた大切なデータベースである。人は思えばそれぞれのデータベースをもっている。おつきあい、交遊DBである。これは年賀状のときだけでなく日常のさまざまな場面でも活用できるはずであるが、たいていは引き出しに1年間眠ったままだ。
自分のことを記憶にとどめておいてくださる方は本当にありがたい。その感謝の気持ちを忘れず、もう1ヶ月過ぎてしまった2002年をしっかり生きたい。