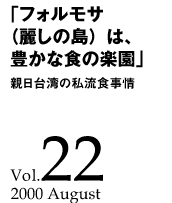|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
最近、日本の若者が数多く、アジア各地に出向いている。近いから、安いから、そして「おいしいから」。昨年の日本人観光客の海外渡航先ランキングでは韓国が1位であったが、台湾も堂々4位。(ちなみに台湾人観光客の渡航先1位は日本)名実ともに「美味しい処」には人が集まってくる。今回は食のメッカ台北について、自分自身の体験や雑感から「台湾の食」について思い付くまま記してみたい。
台湾伝統の食を学ぶなら、まず「朝」に注目
台湾の朝は早い。企業の始業時間も日本より1時間は早い。ご存じ、台北の名物といえば、大量のバイク通勤であるが、朝7時半をすぎると大通りはバイクでいっぱいになる。
人々が元気に走り抜けていくその手を見ると必ずといっていいほど、袋をぶらさげている。バス通勤の人もそうだ。ほとんどの人がバッグとは別に半透明の袋をぶらさげている。これが彼らの「朝ごはん」である。台北のビジネスマン、OLの中には早く会社に着いて、自分のデスクで朝ごはんをとる人も多い。また仕事がはじまってからパンをかぶりつきながら、パソコンに向かっているという姿も珍しくない。
彼らの朝ごはんは、コンビニ、屋台、パン屋などによって支えられている。日本よりもテイクアウトの文化が進んでいる。とくに手軽に買うことができるだけでなく、その場で食べられる屋台は特徴的である。家庭の主婦が或いは夫婦が小さな屋台を営んでいるというのも、台湾ではごくありふれた風景であり、大通りを一本入れば、すぐに屋台に出会うことができる。担仔麺、小龍包、肉や野菜の入った饅頭(具のないものも人気)などが日本人には馴染みが深いがそれ以外にも、とろみのある腸入り酸味のあるスープ、炊き込みごはん(ちまきのよう)、あげパン、豚肉入りの卵焼き、お粥、爆弾のようなおにぎりなどメニューは実に豊富である。これらを小吃と呼ぶそうだ。
屋台料理の特徴は何といっても「速い」「安い」そして「美味しい」こと。日本円で100円もあれば、おなかいっぱいの朝ごはんが楽しめる。とくに目の前で作ってくれるというのが有り難い。時間がないお客を目の前にして世間話をしながら、手際良く調理するその様子はお見事である。また、作り立てのサンドイッチはパンもふかふか、具材はあたたかく美味しいので、行列もできる。町中の屋台では朝ごはんをメインに営業している店も少なくない。台湾の食のマーケットのひとつの柱は、間違いなく「朝食」である。最近では、スターバックスやシアトルをはじめとする西洋式カフェも数多く台北の町に出店、そこでゆっくり新聞を読みながら優雅な朝をおくる若者や紳士ももちろんいるが、伝統的なモバイルフードがやっぱり主力なのである。
ナイトマーケットと「伝統食」
次に台湾の伝統的な食文化を学ぶには、夜市を体験するのがおすすめである。台湾の若者はパワフルである。夜、町のカフェで夜更けまで語り合ったり、夜市(ナイトマーケット)へくり出したりする。このマーケットでは屋台がずらり並び、台湾の伝統的な食をいろいろ味わうことができる。
ウーロンミエン(中国風焼きうどん)、ミイガオ(餅)、ツーシュエタン(豚の血のスープ)、シャンジイ(骨付き鶏モモの空揚げ)、ハイシェンタン(海鮮スープ)愛玉子(ナチュラルゼリー)など種類も豊富で味もなかなかである。とくに台湾の屋台で特徴的なメニューは豆腐料理で、その中でも「臭豆腐」という食品は、字のとおりのもの。(でも、好きな人にはたまらない美味しさだとか)。いずれの屋台料理も朝食と同じく安く30円~300円もあれば満足できる。そんな伝統料理の専門店である屋台に、多くの台湾人が夜な夜な集まってくるのである。いずれも正直「見た目」は美しくないし、美味しそうには見えない。しかし、一度口にすると「!!」と感動が広がる。台湾とくに大都市台北では、台湾、広東、上海、北京、四川、飲茶、満漢全席(満州と漢州の民族融合の豪華料理)などありとあらゆる中国料理が楽しめるだけでなく、また最近では、タイ料理やインド、スイス、ドイツ、アメリカ・・・と世界中の料理も楽しめる各種レストランも増えつつある。そんな町中のレストランと夜市の屋台が共存している。外食文化が異常に発達している都市のひとつが台北である。
台湾流「日本の味覚」と成長するCVS
台湾は九州ほどの国土であり、人口は約2200万人。それほどビッグ!ではないが、そこにコンビニが密集している。台湾には現在約6000件のコンビニが存在している。セブンイレブンは2500件を超え、今や鉄道の主要駅への出店にも積極的で、一見、飽和状態にみえる台湾のコンビニ競争もまだまだ進化しそうな気配である。さて、日本国民の冷蔵庫と化しているのが日本のCVSであるが、台湾でも同様である。台湾のCVS
は、ファミリーマートやニコマートなど日系のCVSもあるが、それ以外のCVS でも日本食の取り入れがさかんである。コンビニにおけるファーストフードは店の個性、他店との差別化においては重要なカテゴリーであるのは日本も台湾も同じであるが、台湾のコンビニには先述のとおり、強敵「屋台」の存在がある。そこに勝つには、伝統の味で勝負でなく、新しいアイデア、個性が求められる。そんなことから台湾のコンビニのFF売り場では数多くの日本食に出会うことができる。
「おにぎり」「おでん」は代表的な例であり、季節商品では「冷麺」「野菜サラダ」も発売され、そして最近ではセブンイレブンが「お弁当」を扱いはじめた。味付け、素材は台湾風であるが、日本のメニューを参考にしたものが多い。
また、台湾のマーケットでは「日式」と入れただけでヒットする商品も多いとか。台湾の食の最前線を短時間で理解するには、コンビニ巡りも不可欠である。
台湾と日本のコンビニの最大の違いは、店内に足を踏み入れたときの匂いである。店内で香ばしい煮玉子の香りが漂っている。食欲をそそられる。そこが台湾風なのである。私はこの香りが大好きである。
台湾では、ここ何年か日本ブームである。ファッションもテレビドラマも、そして食も然りである。最近では、街角に日本のラーメン屋も進出し、大変な活況である。韓国の焼肉まで「日式」としてとらえられているのも面白い。
台湾の「食文化」に学びたいこと
台湾人は、「日本の食の加工技術は優れている」とよくいう。時間が立ってもおいしく見える、また実際に味が変わらない技術に長けているそうだ。一方、台湾ではその辺りでは未熟であり、衛生面も含め、日本を加工食の先駆者として尊敬してくれているようだ。しかし、その一方で、私はこの1年に何回か台湾へ赴き、現地の食を体験するごとに、台湾の食の素晴らしさに感動し、学ぶことが多いというのも事実である。
まず、漢方を含めた自然の素材をうまく食事に取り入れていること。日本人以上に自然志向であると思う。
次に伝統と現代が見事に共存していること。昔から人々が愛してきた食の場面が今も亡くならず生きている。そう、おふくろの味がまだまだ残っている。
マーケットサイズがさほど大きくないにも関わらず、食については激戦の地であろう。人々は「食」に大変コンシャスである。
最後に、台湾のコンビニの商品担当者がいつも言うことを挙げておこう。
「日本の味に負けないものを作る自信はあります」。この言葉に妙に納得してしまうのも事実である。